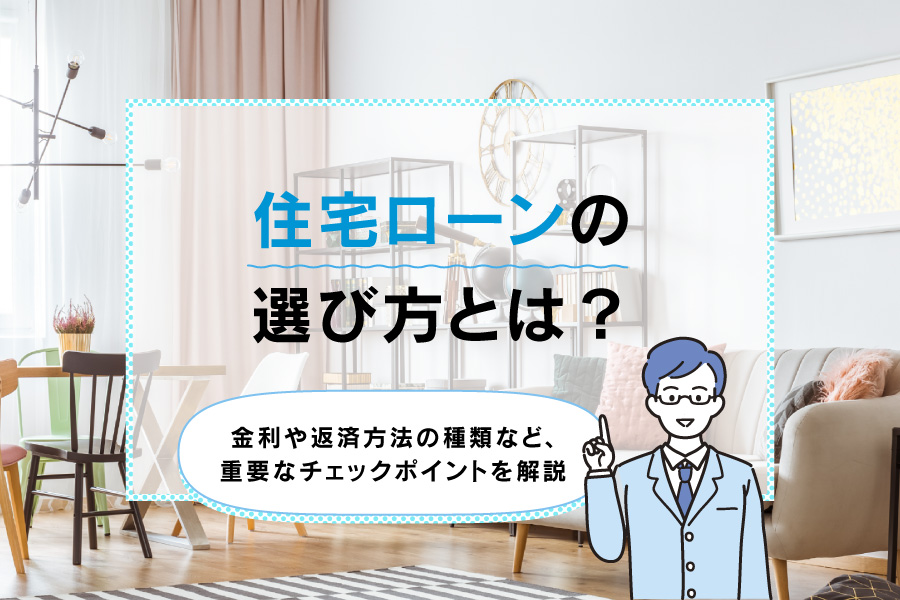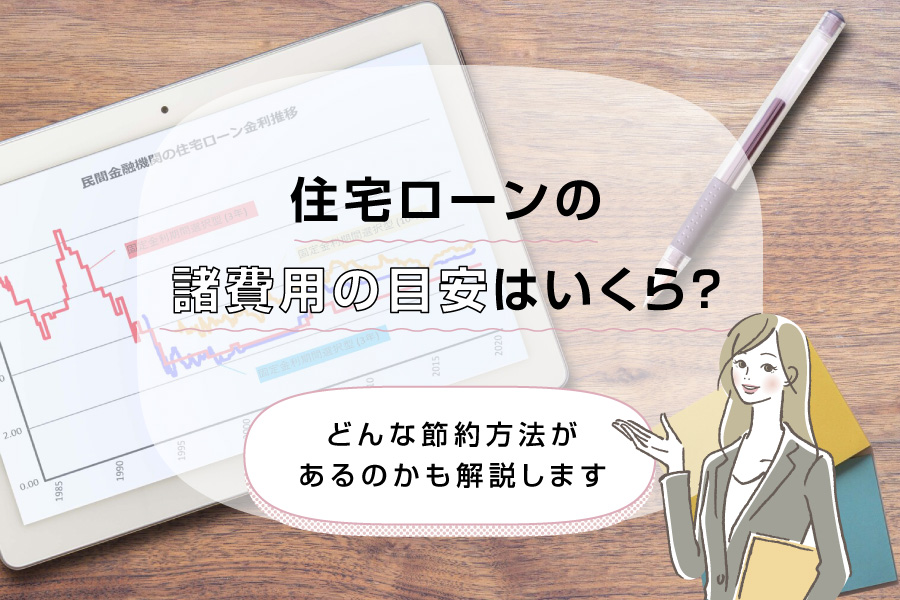【2025年最新】住宅ローンの金利は今後どうなる?今後の金利上昇リスクを踏まえた住宅ローンの選び方
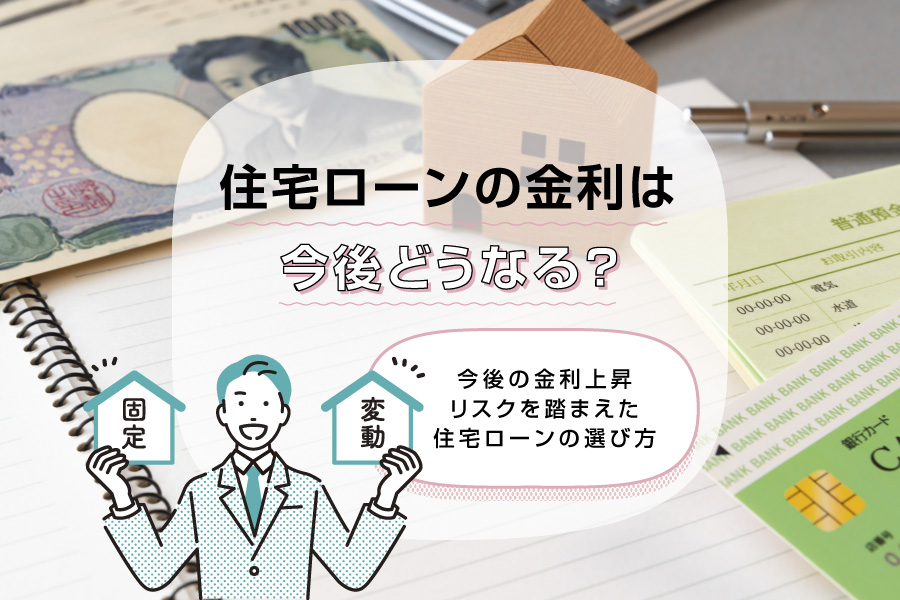
- 2022年10月13日
- 2025年4月18日
日本銀行(以下、日銀))は2025年1月24日の金融政策決定会合で、政策金利を0.5%程度に引き上げる追加の利上げを決定しました。2024年3月のマイナス金利解除以降、日銀の金融政策は「金利のある世界」に舵を切っています。
今後の住宅ローンの金利はどうなるのでしょうか。
この記事では、政策変更によって今後の変動金利・固定金利はどう動くのか、借入中の住宅ローンにはどのような影響があるのか、金利上昇リスクを踏まえた住宅ローンの選び方を解説します。
今後の住宅ローンの金利はどうなるのでしょうか。
この記事では、政策変更によって今後の変動金利・固定金利はどう動くのか、借入中の住宅ローンにはどのような影響があるのか、金利上昇リスクを踏まえた住宅ローンの選び方を解説します。
目次
2024年以降の日銀政策の振り返り
2024年に入り、日本の金融政策は大きな転換点を迎えました。2024年以降の日銀金融政策決定会合での決定のうち、住宅ローン金利に大きく関連する事項を以下にまとめました。
2024年3月19日:マイナス金利解除、17年ぶりの利上げへ
マイナス金利解除、イールドカーブ・コントロール撤廃など金融政策枠組みの見直しを決定。
2024年7月31日:政策金利の引き上げ、国債買入額の半減へ
政策金利の誘導水準を0.25%程度に引き上げるとともに、月間の長期国債買入れ予定額を26年1-3月にかけて3兆円程度にまで減額する計画を決定。
2025年1月24日:政策金利を追加で0.25%引き上げ
政策金利の誘導水準を0.5%程度に引き上げを決定
では今後の住宅ローンの金利は今後どうなるのでしょうか。
次に変動金利・固定金利に分けて今後の動きについて説明します。
2024年3月19日:マイナス金利解除、17年ぶりの利上げへ
マイナス金利解除、イールドカーブ・コントロール撤廃など金融政策枠組みの見直しを決定。
2024年7月31日:政策金利の引き上げ、国債買入額の半減へ
政策金利の誘導水準を0.25%程度に引き上げるとともに、月間の長期国債買入れ予定額を26年1-3月にかけて3兆円程度にまで減額する計画を決定。
2025年1月24日:政策金利を追加で0.25%引き上げ
政策金利の誘導水準を0.5%程度に引き上げを決定
では今後の住宅ローンの金利は今後どうなるのでしょうか。
次に変動金利・固定金利に分けて今後の動きについて説明します。
変動金利・固定金利の指標の違いと今後の動き
変動金利と固定金利の指標の違い
住宅ローンの変動金利と固定金利は、元となる指標が異なります。
【変動金利】
変動金利は、借入期間中に適用される金利が変動する金利タイプのことです。多くの金融機関で短期プライムレートを指標に金利を決めています。短期プライムレートとは、優良企業への1年未満の短期貸し出しにおける最優遇金利であり、日銀の政策金利の影響を受けます。
【固定金利】
固定金利は「新発10年国債利回り」などの長期金利を参考に決定されるといわれています。利回りの水準は、主に国内外の投資家が参加する市場取引で決定されます。一般的に国債の利回りが上昇すると、固定金利も上昇する傾向にあります。
住宅ローンの変動金利は「短期金利は日銀の金融政策の動向」に、固定金利は「長期金利は市場参加者の金利見通し」にそれぞれ影響を受けやすいといわれています。
【変動金利】
変動金利は、借入期間中に適用される金利が変動する金利タイプのことです。多くの金融機関で短期プライムレートを指標に金利を決めています。短期プライムレートとは、優良企業への1年未満の短期貸し出しにおける最優遇金利であり、日銀の政策金利の影響を受けます。
【固定金利】
固定金利は「新発10年国債利回り」などの長期金利を参考に決定されるといわれています。利回りの水準は、主に国内外の投資家が参加する市場取引で決定されます。一般的に国債の利回りが上昇すると、固定金利も上昇する傾向にあります。
住宅ローンの変動金利は「短期金利は日銀の金融政策の動向」に、固定金利は「長期金利は市場参加者の金利見通し」にそれぞれ影響を受けやすいといわれています。
日銀の利上げで変動金利はどうなる?
変動金利の指標となる「短期プライムレート」は各金融機関毎に政策金利や市場金利を基に決めています。今回の利上げにより、既に「短期プライムレート」の引き上げを発表している各金融機関もあります。変動金利がどのタイミングでどれだけ上げるのかも各金融機関の判断によるので、よく確認しましょう。
【2024年以降の短期プライムレート(主要行)の推移】
(単位 年%)
| 実施日 | 短期プライムレート | 増減 |
|---|---|---|
| ~2024年9月1日 | 1.475 | ー |
| 2024年9月2日~ | 1.625 | +0.15 |
| 2025年3月3日~ | 1.875 | +0.25 |
日銀の利上げで固定金利はどうなる?
日銀の国債買入額の減額の決定を受け、長期金利は今後緩やかに上昇していくものと考えられます。指標となる長期金利が上がるにつれて、固定金利も上がる可能性があります。
ただし、長期金利は金利市場によって日々変動します。日銀の政策金利だけではなく、国内外の経済動向・市場取引の影響を受けるので、今後右肩上がりに上がるとも言い切れません。これから固定金利で住宅ローンを借入を検討中の方や、既に住宅ローンを借入中で固定金利への金利タイプ変更を検討中の方は、長期基準の動向をよく確認しましょう。
借入中の住宅ローンの金利はどうなる?
既に住宅ローンを借り入れしている場合、金利が変わるとどのような影響がある のでしょうか?借入中の金利が変動金利か固定金利かに分けて解説します。
変動金利で借入中の場合
変動金利は、その名のとおり、政策金利の影響を受け金利が変動しますが、元利均等返済方式かつ変動金利で借り入れの場合は、多くの金融機関に5年ルールと125%ルールがあります。
【5年ルール】
返済額は5年ごとに見直しします。金利が変更になっても、次回の見直しまで返済額は変わりません(元金と利息の内訳は変わります)。
返済額は5年ごとに見直しします。金利が変更になっても、次回の見直しまで返済額は変わりません(元金と利息の内訳は変わります)。
【125%ルール】
返済額は5年ごとに見直ししますが、金利上昇により返済額が大きくなる場合でも、新返済額は前回までの返済額の125%を限度とします。
返済額は5年ごとに見直ししますが、金利上昇により返済額が大きくなる場合でも、新返済額は前回までの返済額の125%を限度とします。
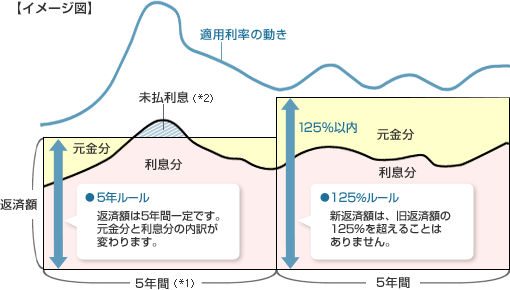
- 10月1日を1回経過する毎に1年経過したものとみなします。
- 適用利率が急上昇して利息分だけで返済額を超えてしまった場合、超過分は未払利息として翌月以降に繰り延べします。
5年ルールが適用されると、金利が上昇した場合でも、次回見直すタイミングまでは現在の返済額に影響はありません。加えて、返済額見直しのタイミングでも現在の125%以上の返済額にはなりません。
しかしながら、上記ルールはあくまで緩和措置です。金利の上昇にともない返済額を大きく上がると家計を圧迫します。住宅ローンを返済ができないケースが出ることを避けるために、返済額を上げる場合は段階を経て徐々に上げていくというのが両ルールの仕組みです。
そのため、金利が上昇した分の利息は「未払利息」として蓄積され、後日支払う必要があります。
5年ルールにより、毎月の返済額は5年間変わりませんが、いずれ未払利息を支払うことになり、返済総額としては増加するため注意が必要です。未払利息の支払いタイミングは、金融機関によって異なります。
しかしながら、上記ルールはあくまで緩和措置です。金利の上昇にともない返済額を大きく上がると家計を圧迫します。住宅ローンを返済ができないケースが出ることを避けるために、返済額を上げる場合は段階を経て徐々に上げていくというのが両ルールの仕組みです。
そのため、金利が上昇した分の利息は「未払利息」として蓄積され、後日支払う必要があります。
5年ルールにより、毎月の返済額は5年間変わりませんが、いずれ未払利息を支払うことになり、返済総額としては増加するため注意が必要です。未払利息の支払いタイミングは、金融機関によって異なります。
また、5年ルール・125%ルールは返済額には適用されますが、金利そのものには適用されません。住宅ローンの利息は、住宅ローン残高(元金)に対する金利で計算されます。変動金利の急激な金利上昇が続いた場合、5年ルールや125%ルールで返済額は大きく上がらなくても、返済に占める利息の割合が多くなり、元金の返済が進まない可能性があります。
また、元金均等返済方式の場合は、変動金利で借り入れしていても、5年ルールや125%ルールは適用されません。毎回の返済額は、お借入元本額を返済回数で割った均等額に1ヵ月ごとの利息支払い額を加えた金額となり、利息支払い額の変動額に上限はありません。
変動金利で借入中の場合、まずは自分の借りている住宅ローンの内容をよく把握しておくことが大切です。5年ルールや125%ルールが適用になるのか、借入利率はどうなっているのか、返済予定表等でよく確認しておきましょう。
固定金利で借入中の場合
固定金利で借り入れしている場合、選択した固定期間は金利・返済額が確定しています。
また、フラット35を代表する全期間固定金利で借り入れの場合は、借入当初から完済時まで金利が確定しており、借入中の金利変動を心配する必要はありません。
ただし、固定10年など一定期間の固定金利を選択している場合は、固定期間中は今回の政策変更の影響はありませんが、固定金利期間終了のタイミングでは変動金利または固定金利を選ぶことになり、その時点では金利が上昇している可能性もある点には注意が必要です。
また、フラット35を代表する全期間固定金利で借り入れの場合は、借入当初から完済時まで金利が確定しており、借入中の金利変動を心配する必要はありません。
ただし、固定10年など一定期間の固定金利を選択している場合は、固定期間中は今回の政策変更の影響はありませんが、固定金利期間終了のタイミングでは変動金利または固定金利を選ぶことになり、その時点では金利が上昇している可能性もある点には注意が必要です。
金利上昇リスクを踏まえた住宅ローン選びを

今後の金利上昇にそなえた対応方法にはどのようなものがあるでしょうか。
変動金利を選ぶ場合は、繰り上げ返済や貯蓄を検討する
変動金利は、今後も金利があまり変動しない、または変動したとしても固定金利ほどの金利水準まで上がらないと考えている人に合った金利タイプです。将来、金利がいつ、どれくらい上がるのかを予想することはなかなか難しいでしょう。ただし、変動金利を選択した場合は、将来の金利上昇が起こりうる可能性も考慮すべきです。
金利が上昇した際には、繰り上げ返済をうまく活用することも選択肢のひとつです。
一部繰り上げ返済とは、毎月の返済とは別に、住宅ローン残高(元金)の一部を任意のタイミングで返済することです。住宅ローンの利息は住宅ローン残高(元金)に対する金利で計算されるため、一部繰り上げ返済で住宅ローン残高(元金)を減らすことにより金利上昇による利息への影響を小さくすることができます。
将来の金利上昇による返済額の増加を防ぐためには、ローン残高を減らしておくことが有効といえるでしょう。
ただし、繰り上げ返済により手元の資金は減少します。繰り上げ返済後に、急にまとまった資金が必要になる可能性もあります。繰り上げ返済はご自身の今後のライフプランに合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。
また、繰り上げ返済をするかどうかとは別に、金利が上昇しても対応できるように貯蓄をふやすこともおススメです。
金利が上昇した際には、繰り上げ返済をうまく活用することも選択肢のひとつです。
一部繰り上げ返済とは、毎月の返済とは別に、住宅ローン残高(元金)の一部を任意のタイミングで返済することです。住宅ローンの利息は住宅ローン残高(元金)に対する金利で計算されるため、一部繰り上げ返済で住宅ローン残高(元金)を減らすことにより金利上昇による利息への影響を小さくすることができます。
将来の金利上昇による返済額の増加を防ぐためには、ローン残高を減らしておくことが有効といえるでしょう。
ただし、繰り上げ返済により手元の資金は減少します。繰り上げ返済後に、急にまとまった資金が必要になる可能性もあります。繰り上げ返済はご自身の今後のライフプランに合わせて無理のない範囲で行うことが大切です。
また、繰り上げ返済をするかどうかとは別に、金利が上昇しても対応できるように貯蓄をふやすこともおススメです。
長期の固定金利を選択する
固定金利は、今後金利が上昇すると考えている人に合った金利タイプです。選んだ固定期間中は金利や返済額が確定するので、返済計画が立てやすいという点が特徴です。子供の教育費など、今後数年間で大きな出費が予想される場合、当面の返済額は金利動向の影響を気にしたくない方は、変動金利ではなく固定金利の選択を検討するのも良いでしょう。
変動金利は、一般的に毎月、もしくは半年に1度の見直しがあるので、借り入れ後に金利をこまめにチェックするのが苦手な方が変動金利を選ぶと、金利タイプを変更したり、ローンを借り換えたりする最適なタイミングを見逃すことがあります。そういった方は、最初から固定金利を選んでおくのも一つの賢い選択肢です。そうすることで、金利の変動に応じて住宅ローンを見直す必要がなくなります。
既に変動金利で借入中の場合、今の金融機関で借入中のまま金利タイプを固定金利に切り替えることや、他の金融機関で借り換えることも選択肢になります。
前者の金利タイプの変更は、契約内容によっては他の金融機関で借り換えるよりも高い金利水準になる場合がある一方、後者の他金融機関での借り換えの場合には一般的に事務手数料や登記費用が改めて必要になります。
ご自身の契約内容をよく確認し、金融機関に相談するなどしてメリットがあるか見極めていくことが大切です。
変動金利は、一般的に毎月、もしくは半年に1度の見直しがあるので、借り入れ後に金利をこまめにチェックするのが苦手な方が変動金利を選ぶと、金利タイプを変更したり、ローンを借り換えたりする最適なタイミングを見逃すことがあります。そういった方は、最初から固定金利を選んでおくのも一つの賢い選択肢です。そうすることで、金利の変動に応じて住宅ローンを見直す必要がなくなります。
既に変動金利で借入中の場合、今の金融機関で借入中のまま金利タイプを固定金利に切り替えることや、他の金融機関で借り換えることも選択肢になります。
前者の金利タイプの変更は、契約内容によっては他の金融機関で借り換えるよりも高い金利水準になる場合がある一方、後者の他金融機関での借り換えの場合には一般的に事務手数料や登記費用が改めて必要になります。
ご自身の契約内容をよく確認し、金融機関に相談するなどしてメリットがあるか見極めていくことが大切です。
金利タイプに迷う場合はミックスも選択肢に
固定金利タイプには一定期間金利上昇の影響を受けないメリットがある一方、変動金利タイプには金利の低さという魅力があります。
家計に比較的余裕があり、金利上昇局面にも対応できる方は、変動金利タイプで低金利を享受するという選択も有力です。ただし、今後どの程度まで金利が上昇するかは誰にもわかりません。
これから借り入れを検討中あるいは他の金融機関での借換を検討されている方で、変動金利と固定金利のどちらにするか迷う場合は、2つを組み合わせるのもおススメです。
変動金利と固定金利を組み合わせた住宅ローンは、固定金利のものと比べて毎月の返済額を抑えられるうえ、金利上昇のリスクにもある程度対応できるとされています。
家計に比較的余裕があり、金利上昇局面にも対応できる方は、変動金利タイプで低金利を享受するという選択も有力です。ただし、今後どの程度まで金利が上昇するかは誰にもわかりません。
これから借り入れを検討中あるいは他の金融機関での借換を検討されている方で、変動金利と固定金利のどちらにするか迷う場合は、2つを組み合わせるのもおススメです。
変動金利と固定金利を組み合わせた住宅ローンは、固定金利のものと比べて毎月の返済額を抑えられるうえ、金利上昇のリスクにもある程度対応できるとされています。
まとめ
日銀の追加利上げを受け、各金融機関は預金金利の引き上げを相次いで発表しました。
「金利のある世界」では、預金で利子がもらえるという家計にとってプラスの恩恵もある一方、お金を借りている人にとっては借入金利が上昇するというマイナスの影響もあります。
将来の生活設計(ライフプラン)において、出産や、教育費の増加、親の介護など、不確定要素が多い人は、金利の上昇による将来の支出の変化に対応できるように、固定金利の活用で金利上昇リスクを減らす、繰り上げ返済をうまく活用して、早めにローン残高を減らしていくといった方法が有効です。
また、貯蓄があると予期せぬ事態にも柔軟に対応できます。そのため、返済額を無理のない範囲に設定し、住宅ローン返済をしながら貯蓄ができるような資金計画を立てることを検討しましょう。
返済が長期にわたる住宅ローンでは、既に借入中の人も、これから借り入れを検討する人も、今後の金利の見通しをよく考え、ご自身のライフプランに合った金利タイプを選ぶことをおススメします。
「金利のある世界」では、預金で利子がもらえるという家計にとってプラスの恩恵もある一方、お金を借りている人にとっては借入金利が上昇するというマイナスの影響もあります。
将来の生活設計(ライフプラン)において、出産や、教育費の増加、親の介護など、不確定要素が多い人は、金利の上昇による将来の支出の変化に対応できるように、固定金利の活用で金利上昇リスクを減らす、繰り上げ返済をうまく活用して、早めにローン残高を減らしていくといった方法が有効です。
また、貯蓄があると予期せぬ事態にも柔軟に対応できます。そのため、返済額を無理のない範囲に設定し、住宅ローン返済をしながら貯蓄ができるような資金計画を立てることを検討しましょう。
返済が長期にわたる住宅ローンでは、既に借入中の人も、これから借り入れを検討する人も、今後の金利の見通しをよく考え、ご自身のライフプランに合った金利タイプを選ぶことをおススメします。
執筆者:株式会社 三菱UFJ銀行
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行で住宅ローンをお申し込み
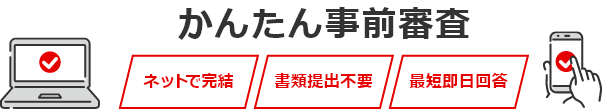

- 受付状況等により審査に日数がかかる場合があります
あわせて読みたい
株式会社 三菱UFJ銀行
(2025年4月18日現在)