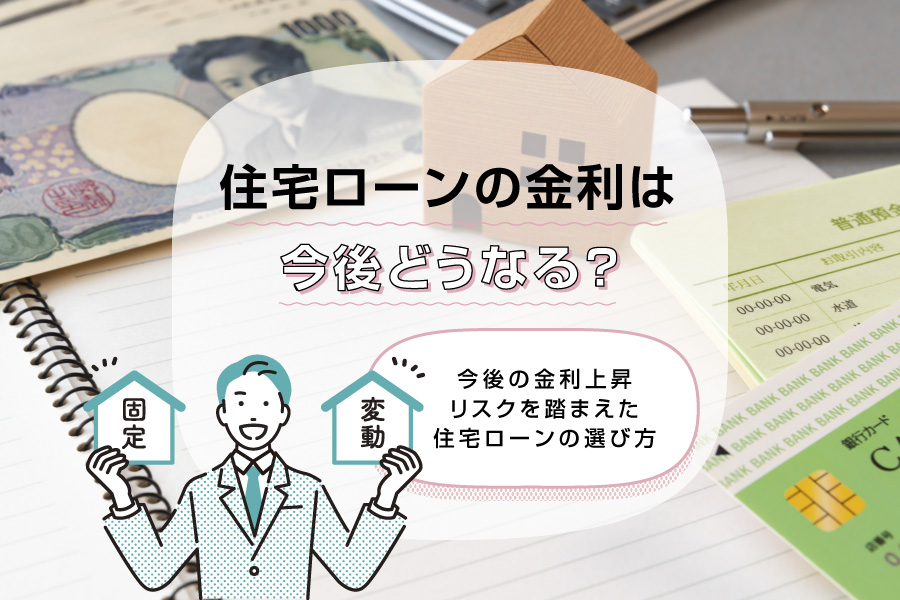住宅ローンの変動金利と固定金利の仕組みとは?メリット・デメリットと選び方を解説!
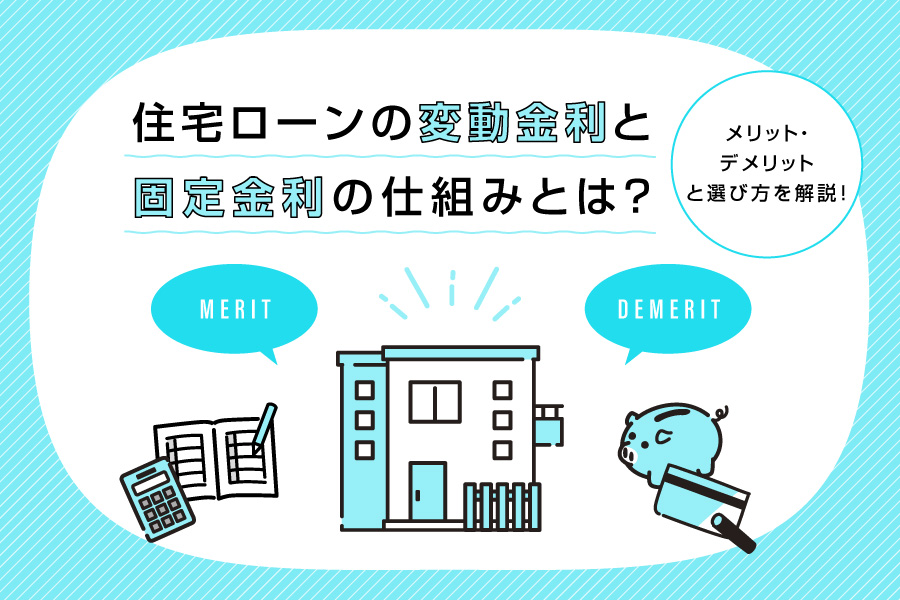
公開日:2022年5月16日
更新日:2025年3月14日
更新日:2025年3月14日
住宅ローンの金利には、変動金利・固定金利・全期間固定金利の3つの金利タイプがあります。
自分に合った金利タイプを選ぶためにも、金利の仕組みや特徴を知ることが大切です。
本記事では、3つの金利タイプの特徴やメリット・デメリット、どんな人に向いているかについて分かりやすく解説します。
借入時点の金利だけで比較すると、変動金利型の金利が一番低く、次に固定金利、全期間固定金利の順で金利が高くなっています。
自分に合った金利タイプを選ぶためにも、金利の仕組みや特徴を知ることが大切です。
本記事では、3つの金利タイプの特徴やメリット・デメリット、どんな人に向いているかについて分かりやすく解説します。
借入時点の金利だけで比較すると、変動金利型の金利が一番低く、次に固定金利、全期間固定金利の順で金利が高くなっています。
目次
住宅ローンの金利3種類の違い
- 変動金利型
- 当初固定期間選択型
- 全期間固定金利型
変動金利型は決められた基準日で金利が見直される
変動金利型は、住宅ローンに適用される金利が変動するタイプの金利です。金利の見直しは融資元の銀行が定めた基準日に行われており、一般的には6ヵ月ごとの年2回ですが、毎月見直しを行う銀行もあります。
住宅ローン金利タイプの中では返済期間中に、最も政策金利の影響を受けやすい特徴がありますが、ほかの金利タイプとの比較の中では最も適用金利が低くなる傾向があります。
当初固定期間選択型は一定期間金利が固定
当初固定期間選択型は、一定期間金利が固定できる金利タイプです。一定期間のみ固定金利が適用されますが、その期間が終了すると、そのときの金利水準での固定金利または変動金利を選択できます。
変動金利を選択した場合は、変動金利型と同様に銀行が定めた基準日に金利が見直されます。
全期間固定金利型は返済総額に変更なし
全期間固定金利型は、住宅ローンを借り始めた時点で決定された金利から適用金利が変わらず、完済まで毎月一定額を返済する金利タイプです。
3種類の金利タイプの中では最も金利が高くなりますが、返済額が変わらないため返済計画を立てやすくなります。
住宅ローンの各金利タイプのメリット・デメリットは?
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 変動金利型 |
|
|
| 当初固定期間選択型 |
|
|
| 全期間固定金利型 |
|
|
変動金利型のメリットには、同時期の住宅ローンの中で一番金利が低いことが挙げられます。
2025年2月現在においては、1%を下回る水準で借りることができる場合も多いです。しかしながら、将来金利が上がれば返済額がふえる可能性があります。
変動金利で元利均等返済の場合には、金利が急上昇しても借入開始から5年間は毎月の返済額が変わらないというルールがあります。
また6年目以降の見直しで返済額が増えたとしても、最大で1.25倍までしか引き上げられません。しかし、実際に1.25倍に返済額がふえると、多くの住宅ローン利用者は返済が苦しくなるのではないのでしょうか。1.25倍を超えた分は返済が免除されるわけではなく、その後に金利が下落した際に調整され返済額に上乗せするか、返済最終日にまとめて返済しなければなりません。また、毎月の返済額は変わらなくても、金利が変わることにより、返済額のうちの元金と利息の内訳は変わるので、返済総額が変わります。
したがって、金利が上昇すると、利息の支払いが増えることになります。
一貫して低金利が続いている変動金利ですが、将来的には金利が上昇するリスクを理解のうえ選択する必要があります。
2024年3月にマイナス金利が解除されて以降、政策金利が段階的に引き上げられており、2025年1月24日の日銀による金融政策決定会合では、政策金利を0.5%程度に引き上げる追加の利上げを決定しました。日銀の金融政策は「金利のある世界」に舵を切っています。
このような日銀の政策転換により、今後変動金利は金利が上昇する可能性があります。将来、金利がいつ、どれくらい上がるのかを予想することは難しいですが、変動金利を選択した場合は将来の金利上昇が起こりうる可能性も考慮しましょう。
このような日銀の政策転換により、今後変動金利は金利が上昇する可能性があります。将来、金利がいつ、どれくらい上がるのかを予想することは難しいですが、変動金利を選択した場合は将来の金利上昇が起こりうる可能性も考慮しましょう。
当初固定期間選択型は、適用金利が変動金利と全期間固定金利型との中間の水準となることが多く、一定期間は固定金利であり、その間は金利上昇しても返済額は変わりません。しかし、短期金利の上昇中に固定期間が終了すると、その後に適用される変動金利が上昇し、返済額がふえるリスクは変動金利と同様です。
一方、全期間固定金利型は、変動金利より借入時点では適用金利が高くなってしまいますが、借入時の金利が返済終了まで適用されるため、借入時に返済総額と毎月の返済額が決まり、そのあと変わることがありません。
毎月の返済額を余裕もって設定すれば将来収入減少があった場合にもそなえられますし、金利が上昇しても返済額の増加を防げるというメリットがあります。
住宅ローンを借り入れする人の7割以上は変動金利型を選択

住宅金融支援機構が2023年4月に行った「住宅ローン利用者の実態調査」によると、2022年10月~2023年3月に住宅ローン(フラット35含む)を利用した人が選んだ金利タイプは以下の割合となっています。
- 変動金利型:72.3%
- 固定金利選択型:18.3%
- 全期間固定型:9.3%
前回調査対象である2022年10月調査(2022年4月~9月)に比べると、当初固定期間選択型および全期間固定金利型の割合は減少し、変動金利型の割合は上昇し7割以上の人が選択しているという結果となりました。
(出典:住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査2023年4月調査をもとに作成)
なお、上記調査後の2024年3月には日銀の金融政策決定会合で、大規模緩和策の一環で実施していた「マイナス金利政策」を解除することを決定、また同年7月、2025年1月と追加利上げを実施しました。このような金利上昇局面においては、今後住宅ローン金利も変更される場合がありますので、引き続き注視しましょう。
(出典:住宅金融支援機構 住宅ローン利用者の実態調査2023年4月調査をもとに作成)
なお、上記調査後の2024年3月には日銀の金融政策決定会合で、大規模緩和策の一環で実施していた「マイナス金利政策」を解除することを決定、また同年7月、2025年1月と追加利上げを実施しました。このような金利上昇局面においては、今後住宅ローン金利も変更される場合がありますので、引き続き注視しましょう。
自分にぴったりの金利タイプの選び方
住宅ローンは一般的に10年から35年と長期間利用するものです。
経済の変化などにより金利の先行きを見通すのは難しいものですが、今後の返済計画に対する考え方や金利見通しの立て方によって、以下のように金利タイプを選ぶのがおススメです。
変動金利型:今後金利はあまり上がらないと考えている方
過去の動向を踏まえて今後金利はあまり上がらないと考えている方や、経済に興味があり日常的に金利動向をチェックしている人には変動金利型がおススメです。
当初固定期間選択型:一定期間までは返済額を固定したいと考える方
一定期間までは返済額を固定したいと考える方には、当初固定期間選択型がおススメです。
当初固定期間選択型は全期間固定金利型よりも金利が低く、変動金利型よりも金利上昇リスクにそなえやすいのがメリットです。
また、銀行によっては、当初固定期間選択型の金利固定期間を3年・5年・10年などの期間の中から選ぶことができます。多くの銀行では固定期間を3年や5年など短期に設定すると、長期に比べ低い金利が適用されます。銀行によっては変動金利よりも低い金利が適用される場合もありますので、子どもの教育費用などをつみたてやすくなるのは大きなメリットです。
全期間固定金利型:金利は上がるかもしれないと考えている方
今後金利が上がっていくと考えている方は、全期間固定金利型を選ぶと良いでしょう。
3つの金利タイプのうち最も高い金利が適用されますが、契約時点の金利を基準に返済総額が確定するため、金利が上昇する局面にあっても適用金利は変わらず、毎月の返済額がふえることはありません。
全期間固定金利型には長期固定金利が適用される「フラット35」が含まれます。
まとめ
住宅ローンの借入額や返済期間、返済計画やライフプランは人によって異なります。
住宅ローンを組む際には、3つの金利タイプ毎の特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
また、「金利のある世界」では、今後の経済情勢や金利の動向を予想したうえで金利を選ぶことがより重要になります。金利の数値だけでなく、3つの金利タイプの違いをよく理解したうえで選びましょう。
住宅ローンを組む際には、3つの金利タイプ毎の特徴やメリット・デメリットを理解し、自分に合ったものを選ぶことが大切です。
また、「金利のある世界」では、今後の経済情勢や金利の動向を予想したうえで金利を選ぶことがより重要になります。金利の数値だけでなく、3つの金利タイプの違いをよく理解したうえで選びましょう。
執筆者:手塚 裕之(てづか ひろゆき)
監修者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
監修者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行で住宅ローンをお申し込み
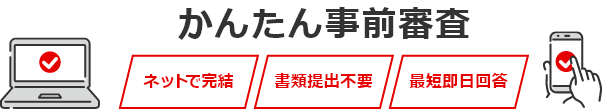

- 受付状況等により審査に日数がかかる場合があります
あわせて読みたい
株式会社 三菱UFJ銀行
(2025年3月14日現在)
(2025年3月14日現在)