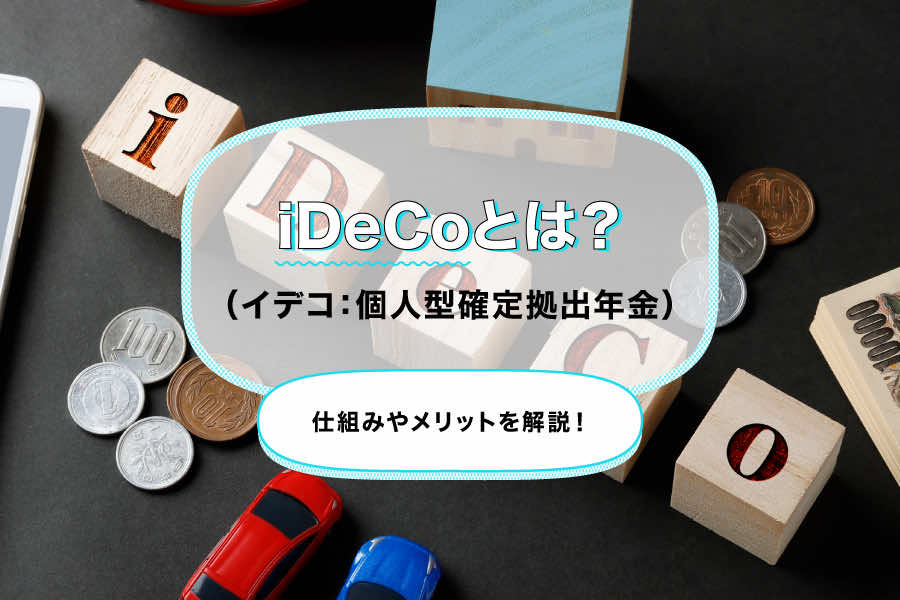【2024年版】iDeCo(イデコ)の掛金の上限額はいくら?職業別の拠出限度額や拠出額を決めるポイントを解説!

- 2022年5月16日
- 2024年12月1日
最近の物価上昇などに不安を感じ、将来のために資産形成をしたいと考え、iDeCoを検討し始めた方も多いのではないでしょうか。
iDeCoは、任意で加入できる私的年金制度です。5,000円から掛金を積み立てられますが、上限額は職業や企業年金の加入状況によって異なります。
iDeCoに加入する場合、自分の上限額はいくらなのでしょうか。掛金の平均額や納付方法についても解説していますので、加入する際の参考にしてみてください。
目次
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)の掛金の上限額は?加入資格や平均額をチェック
iDeCoは毎月5,000円から積立ができます。ただし、掛金の上限額は人によって違うため、自分の限度額がいくらなのか把握しておきましょう。
どのくらいの掛金に設定すればいいのかわからない場合は、目安として平均額も参考にしてください。
iDeCoの掛金の上限額は?
iDeCoは、加入資格によって掛金の上限額が異なります。
加入資格は職業などで決まるため、以下の表でご自身がどれにあてはまるのか確認してみましょう。
| 対象 | 企業年金等(*1)への加入 | 月額/年額の上限 |
|---|---|---|
| 自営業者等 | - | 68,000円/816,000円(*2) |
| 会社員・公務員等 | あり | 20,000円(*3) |
| なし | 23,000円/276,000円 | |
| 専業主婦(夫) | - | 23,000円/276,000円 |
- 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します
- 国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算した金額です
- 下記条件があります
会社員・公務員等の第2号被保険者が確定給付型の他制度(*1)とiDeCoを併用する場合、iDeCoの拠出限度額は2万円です。ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円が上限です。 式で表すと以下のようになります。
iDeCoの拠出限度額(上限2万円)=月額5.5万円 ー(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額)
そのため、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額が高い場合、iDeCoの拠出限度額が減少または拠出できなくなることがあります。
また、以下の加入条件があります。
また、以下の加入条件があります。
- 企業型DC・iDeCoの掛金が年単位拠出でないこと
- マッチング拠出を利用していないこと
- 拠出額が上限内であること
iDeCoの加入資格
加入資格について、もう少しくわしく見てみましょう。
iDeCoの加入資格は、正確には国民年金の被保険者種別によって異なり、第1号・第2号・第3号被保険者に区分されています。
それぞれの違いは以下のとおりです。
| 種別 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
|---|---|---|---|
| 加入制度 | 国民年金 | 国民年金 厚生年金 |
国民年金 |
| 対象者 | 学生・自営業者等 | 会社員・公務員等 | 第2号被保険者に 扶養される配偶者 |
上記の種別ごとに掛金の限度額が異なります。
これまでは60歳未満という年齢要件もありましたが、現在は任意加入被保険者(*1)か厚生年金の被保険者であれば、65歳になるまで加入できます。
- 国民年金の納付済み期間が480ヵ月に足りず、60歳以降も任意で加入する人
ただし、企業年金の加入状況により、拠出限度額が変わります。
なお、以前は企業年金のある会社員等は、規約の定めにより加入できない人も多くいました。
しかし、現在は基本的に誰でもiDeCoに加入できます(勤務先の企業型DCに加入し、マッチング拠出あるいは年単位拠出をしている場合を除く)。
掛金の目安は?平均額をチェック
iDeCoの掛金は、最低5,000円から1,000円単位で設定できます。
長期で加入する制度のため、掛金は無理のない金額を設定することが大切ですが、平均拠出額も参考にして検討してみてください。
| 加入資格 | 月額の平均掛金額 | |
|---|---|---|
| 第1号被保険者 | 27,982円 | |
| 第2号被保険者 | 14,494円 | |
| 分類 | 企業年金なし | 16,763円 |
| 企業年金あり | 11,513円 | |
| 公務員 | 10,984円 | |
| 第3号被保険者 | 14,644円 | |
| 全体 | 16,035円 | |
参考:iDeCo公式サイト「iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入等の概況(2024年8月)」
平均の掛金額は限度額も関係していると考えられますが、年金制度の手厚い第2号被保険者は少なく、国民年金のみの第1号被保険者は多めに積み立てている傾向が見られます。
全体の平均は約16,000円です。あくまでも平均のため、実際にはご自身の状況にあわせて掛金を設定しましょう。
また、最終的な目標金額があれば、そこから掛金を決める方法もあります。
例えば、iDeCoだけで800万円を目指す場合、利回り年1%なら毎月およそ19,000円を30年間積み立てれば達成の見込みがあります。
ただし、目標金額や加入期間によっては毎月の掛金が上限額を超えてしまいますので、NISAなどを上手に組み合わせて運用することも検討しましょう。
掛金を変更したいときは
iDeCoの掛金額は変更できますが、年1回のみです。
変更できる期間は、毎年12月~翌年11月(実際の引き落とし月は1月~12月)の間ですが、被保険者種別を変更するときの掛金額は、変更回数に含まれません。
変更したい場合は以下の書類を金融機関に提出しましょう。
<掛金変更に必要な書類>
加入者掛金額変更届
掛金の引き落としを停止したい場合は、以下の書類を提出する必要があります。
<掛金の引き落とし停止に必要な書類>
加入者資格喪失届
手続き完了まで1〜2ヵ月程度かかるため、変更したい場合は早めに手続きしましょう。
iDeCo(イデコ)の掛金の納付方法
iDeCoの掛金は、毎月の銀行引落が基本ですが、特定の月にまとめて納付する年単位拠出も可能です。ただし事業主が拠出する企業型DCやDB等の他の企業年金制度にも加入する第2号被保険者(会社員・公務員の方)は、掛金の年単位拠出は利用できません。
掛金の納付方法は?
iDeCoの掛金は、銀行口座からの引き落としで納付します。引落日は毎月26日で、休業日の場合は翌営業日に引き落とされます。
初回掛金については、申し込みタイミングにより、申し込み月の翌々月に2ヵ月分引き落とされることがあるため、残高不足に注意しましょう。また、引き落としできなかった場合、追納はできません。
第2号被保険者である会社員や公務員は、勤務先で手続きしてもらい、給与天引きによる納付(事業主払込)も可能です。
事業主払込で納付すれば、年末調整が不要になるメリットはありますが、対応していない企業が多いため、個人口座による銀行引落が基本です。
掛金の引き落としタイミングは?
iDeCoの掛金は、毎月の引き落とし以外に、任意の月にまとめて納付する年単位拠出も可能です。
しかし、事前に掛金と納付月を指定する手続きが必要だったり、iDeCoは経過した月の分しか拠出ができないため(1月に2~12月分の拠出は出来ない)、11月分(12月引き落とし)を含める必要があるなど、いくつか条件がある点には注意しましょう。
年単位拠出の例として、ここでは限度額が月額2万円の場合、特定の月にまとめて納付するケースと、特定の月に増額するケースを見てみましょう。
特定の月にまとめて積み立てるケース
<積立限度額が月額2万円の場合>
| 12月分 (1月引落) |
1月分 (2月引落) |
2月分 (3月引落) |
3月分 (4月引落) |
|
|---|---|---|---|---|
| 拠出額 | 0円 | 0円 | 0円 | 8万円 |
| 繰越合計額 | 2万円 | 4万円 | 6万円 | 0円 |
このケースでは12月分〜2月分を繰り越し、3月分とあわせ、2万円 × 4ヵ月 = 8万円をまとめて納付しています。
特定の月に増額するケース
<積立限度額が月額2万円の場合>
| 12月分 (1月引落) |
1月分 (2月引落) |
2月分 (3月引落) |
3月分 (4月引落) |
|
|---|---|---|---|---|
| 拠出額 | 1万円 | 1万円 | 4万円 | 1万円 |
| 繰越合計額 | 1万円 | 2万円 | 0円 | 1万円 |
このケースでは、毎月1万円を納付しますが、2月分は2万円に増額し、1月分までの繰越合計額(計2万円)をあわせた4万円を納付しています。
繰り越しできる金額は、毎月の掛金と拠出限度額の差額です。
iDeCo(イデコ)のメリットと運用について

iDeCoは、私的年金制度として資産形成に活用できます。さらに税制優遇も受けられるため、具体的にどのようなメリットがあるのか見ていきましょう。
iDeCoのメリットは税の優遇を受けられること
iDeCoの税制優遇メリットは、大きく分けて3つあります。
- 掛金が全額所得控除になる
- 運用益は全て非課税
- 将来受け取るときも各種控除が適用になる
それぞれ確認していきましょう。
メリット1.掛金が全額所得控除になる
iDeCoの掛金は、全額を所得控除できます。それによって所得税と住民税を軽減できるメリットがあります。
所得税と住民税は、1年間の所得に対してかかる税金です。納めた掛金を所得から控除できれば、その分所得が減り、所得税と住民税が軽減される仕組みです。
実際に軽減される税額は、その人の税率と掛金によって異なります。
例えば、所得税率20%の人が年間24万円の掛金を積み立てる場合、一律10%の住民税率とあわせ、掛金の30%分である72,000円もの税金が軽減されます。
<所得税率20%の人が年間24万円を積み立てる場合の税軽減効果>
年間掛金24万円 × 30%(所得税率20%+住民税率10%)=72,000円
三菱UFJ銀行のホームページからも、税金の軽減効果をシミュレーションができるので、気になる人は試してみてください。
メリット2.運用益は全て非課税
金融商品を運用して利益を得た場合、通常、利益に対して20.315%の税金がかかります。
しかし、iDeCoでは運用益が全額非課税になり、運用で得た利益はそのまま元本に再投資されます。そのため、同じ運用をしても利益から税金が引かれない分、運用資産の増幅が期待できます。
仮に毎月2万円を積み立て、年率1%で25年間運用した場合、運用益は約81万円になります。
本来ならここから20.315%が課税され、およそ163,000円の税金が引かれます。しかし、iDeCoでの運用は利益をそのまま受け取れるため、手元に運用益を多く残せることがメリットです。
メリット3.将来受け取るときも各種控除が適用になる
iDeCoの運用資産を受け取るときは、年金か一時金(金融機関によっては併用)で受け取り、一定額まで税金がかかりません。
年金で受け取るときは「公的年金等控除」、一時金で受け取るときは「退職所得控除」が適用され、税負担を軽くして運用資産を受け取れる仕組みです。
公的年金等控除は所得や年齢で控除額が異なりますが、公的年金等以外の合計所得金額が1,000万円以下の場合、65歳未満の方は年金額130万円未満の場合は年間60万円まで、65歳以上の方は330万円未満の場合は年間110万円まで、公的年金などとiDeCoの年金をあわせた収入が非課税で受け取れます(2024年12月1日時点)。
退職所得控除については、iDeCoの積立期間を勤続年数とみなし、以下のとおり控除額が決まります。
| 勤続年数(積立期間) | 退職所得控除額 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 勤続年数(最低控除額は80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 ×(勤続年数 − 20年) |
iDeCoには、年金でも一時金でも税負担を抑えて運用資産を受け取れるメリットがあります。
iDeCoの運用について
iDeCoに積み立てたお金は、将来受け取るまで自分で運用をしていきます。商品は大きく分けて、「元本確保型」と「投資信託」があります。
| iDeCoの商品カテゴリー | 特徴 |
|---|---|
| 元本確保型 |
|
| 投資信託 |
|
実際には上記2つのカテゴリーの中で、金融機関ごとにさまざまな商品がラインアップされています。
最終的には自身でどの商品にするかを選ぶ必要はありますが、商品の内容がよくわからない場合は、金融機関で説明を聞き、商品選びの参考にしてみましょう。
相談は、店舗ではなく電話のみで受け付けている金融機関もあるので、まずはホームページを確認することをおススメします。
運用途中で受給する場合の注意点
iDeCoは原則60歳になるまで引き出しできませんが、一定の障害状態や本人が亡くなった場合は60歳未満でも給付の対象になります。
一定の障害状態の場合は「障害給付金」として本人が受け取り、本人が亡くなった場合は「死亡一時金」としてご遺族が受け取れます。
また、特定の条件に該当すれば、iDeCoを解約して「脱退一時金」を受け取ることもできます。ただし、条件が厳しいため、通常は受け取れないと認識しておきましょう。
なお、いずれの場合でも運営管理機関に連絡して手続きが必要です。
なぜiDeCo(イデコ)を始めたのか?FPの体験談
ここまでiDeCoについて紹介をしてきましたが、筆者も10年以上加入しています。
加入のきっかけは、当時の勤務先で企業型DCに加入しており、退職時に運用資産をiDeCoに移したことです。
それから現在も積み立てを続けている理由は、税制優遇の効果が大きく、資産形成をスピードアップできると考えているからです。
税制優遇効果が大きく資産形成のスピードアップになる
税制優遇については、掛金の全額所得控除が強力だと考えています。仮に税率が30%だとすれば、運用益がなかったとしても掛金の30%分の税金が軽減されます。
先ほど計算したとおり、年間24万円の掛金なら72,000円の軽減効果です(状況により税制優遇効果は変わります)。
これが毎年続くと考えれば非常に大きなことです。私の場合は軽減した税金分のお金をNISAなどに回し、さらに運用して増やすようにしています。
そうすることで運用元本の増え方が大きくなり、資産形成のスピードアップにもつながります。
- 運用商品には価格変動リスクがあり、売却や受け取りのタイミングによっては元本を下回る場合もあります
運用中のFPが考えるiDeCoのポイント
iDeCoならではのポイントには、強力な税制優遇効果もありますが、途中解約できないことも資産形成をするうえでメリットといえます。
カンタンに引き出しができてしまうと、人によっては何かあったときに解約して使ってしまうことが考えられるからです。
もちろん引き出し制限がなくても問題なく貯蓄できる人もいますが、制限があることで使ってしまうリスクを抑えることができます。
NISAや保険などはいざとなったら解約できてしまうため、iDeCoは、貯蓄が苦手な人や将来に向けて着実に積立がしたい人に向いているのではないでしょうか。
まとめ
iDeCoは、原則60歳未満の国民年金被保険者なら誰でも加入でき、税制優遇メリットのある私的年金制度です。
掛金は最低5,000円から1,000円単位で自由に設定できますが、限度額は加入区分によって異なります。
iDeCoに加入する際は、ご自身の限度額を確認し、掛金をいくらにするか検討しましょう。
60歳未満での引き出しはできませんので、積立を続けていける金額に設定し、無理なく資産形成をしていきましょう。
執筆者:國村 功志(くにむら こうじ)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、一種外務員資格
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、一種外務員資格
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行でiDeCoを始める方法
あわせて読みたい
ご注意事項
iDeCoをお申し込みいただく前に、下記についてご確認ください。
- 原則、60歳まで引き出し(中途解約)ができません
- 脱退一時金を受け取れるのは一定の要件を満たす方に限られます。
- ご本人の判断で商品を選択し運用する自己責任の年金制度です
- 確定拠出年金制度では、ご加入されるご本人が自らのご判断で、商品を選択し運用を行いますので、運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
- 当行から特定の運用商品の推奨はできません。
- 運用商品の主なリスクについて
- 預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険制度の対象となります。
- 当行のiDeCoで取り扱う保険は元本確保型商品です。ただし、運用商品を変更する目的で積立金を取り崩す場合は、市中金利と残存年数等に応じて解約控除が適用されるため、結果として受取金額が元本を下回る場合があります。
- 投資信託は価格変動商品です。預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。運用実績は市場環境等により変動し、元本保証はありません。また、当行でお取り扱いする投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 預金、保険および投資信託は異なる商品であり、それぞれリスクの種類や大きさは異なります。
- 初回手続き時、運用時、給付時等で、各種手数料がかかります
- iDeCoには、初回手続き手数料・毎月の事務手数料・資産管理手数料・運営管理機関手数料・給付事務手数料等がかかります。
- 手数料は、加入者となられる方は毎月の掛金から、運用指図者となられる方は積立金から控除されます。年金でお受け取りになられる方は給付額から控除されます。
- 60歳になっても受け取れない場合があります
- 50歳以上60歳未満で加入した場合等、60歳時点で通算加入者等期間(*)が10年に満たない場合は、受給可能年齢が引き上げられます。
- 60歳以上で新規加入した場合、加入から5年経過後に受給可能となります。
- 通算加入者等期間は、iDeCoおよび企業型DCにおける加入者・運用指図者の期間の合算となります。
株式会社 三菱UFJ銀行
(2025年1月27日現在)