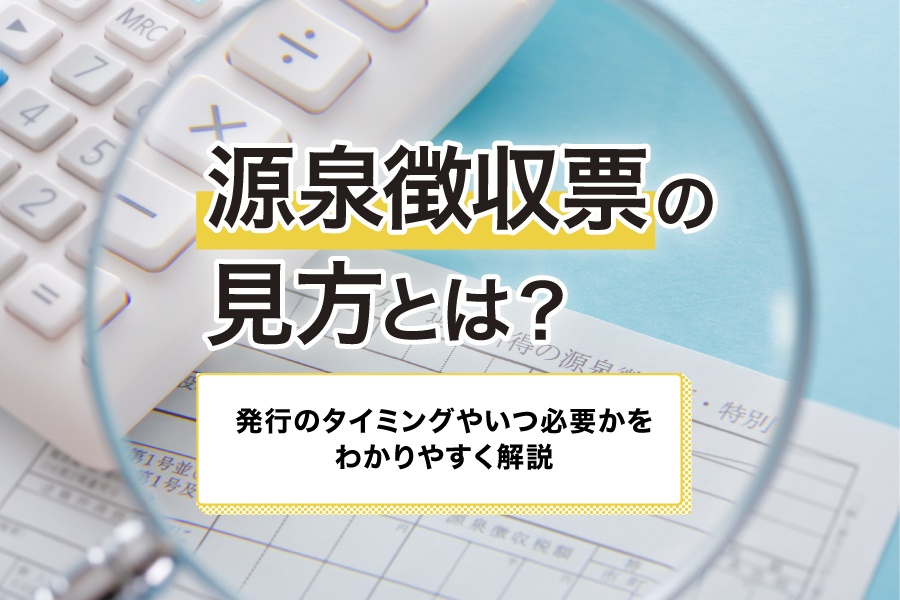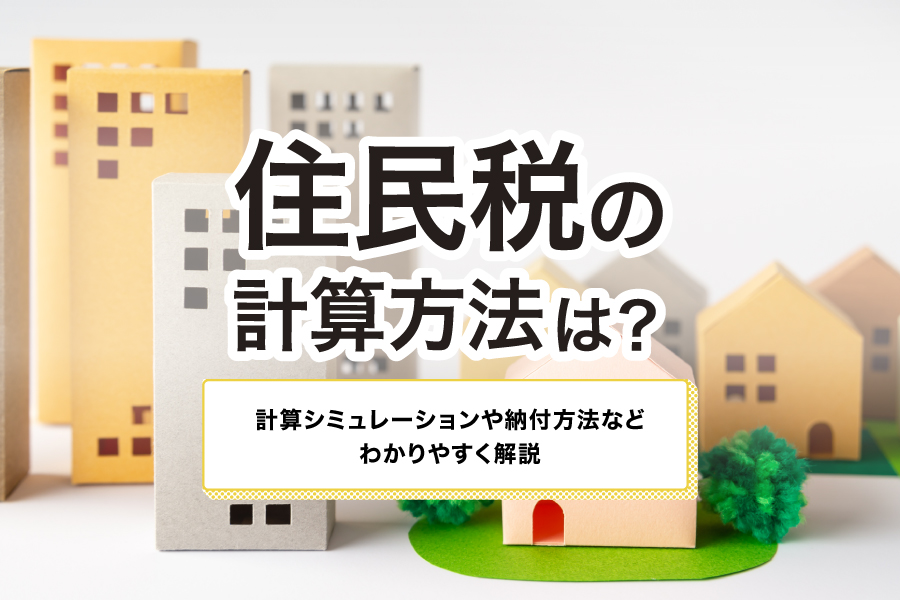住宅ローンを徹底比較!知っておきたい金利の相場と利息の計算方法

- 2021年5月19日
- 2025年3月14日
住宅ローンには「金利タイプ」別に3つの種類があります

- 変動金利型
- 固定金利期間選択型
- 全期間固定金利型
変動金利型住宅ローンの特徴やメリット・デメリット
変動金利型の住宅ローンの特徴は、借入期間中、半年ごとに金利が見直されることです。ただし、金利が半年ごとに変わっても返済額は5年ごとの見直しとなり、5年間返済額は変わりません。
またその返済額の見直し幅は、見直し前の返済額の1.25倍(1.25倍ルール)までとされている場合が多いです。これは見直しによる返済負担の急激な上昇を抑えるためです。
変動金利型のメリット |
金利下降局面では、金利低下のメリットをいち早く受ける |
ほかの金利タイプより一般的に金利が低く、比較的金利負担が小さい |
|
| 変動金利型のデメリット |
金利上昇局面では、金利負担が増加しやすい |
返済額が5年ごとに変わる可能性があるため、返済計画が立てにくい |
|
| 金利上昇により利息負担割合が増える場合、借入元金がなかなか減らない状態になる | |
| 金利上昇により利息額が毎回の返済額を超えてしまうと元金がまったく減らず、利息も支払いきれない「未払利息」が発生する可能性がある |
変動金利型に向いている人とは
ほかの金利タイプと比較して金利の低い傾向にある変動金利型は総返済額を抑えるには有利ですが、一方で、金利変動リスクがもっとも高いことに注意が必要です。そのため、将来金利が上昇しても繰り上げ返済なども含め、返済できる経済的余裕がある人向けと言えます。
また、借入額が少ない場合や借入期間が短い期間で返済可能な人も、金利上昇による返済額の増加が比較的少なく済むので向いていると言えるでしょう。
固定金利期間選択型住宅ローンの特徴やメリット・デメリット
固定金利期間選択型のメリット |
固定金利期間中は金利変動リスクを回避できる |
金利変動リスクを抑えつつ、比較的低金利を享受できる |
|
| 金利下降局面では、固定金利期間終了時に他行への借り換えなどの対応をしなくても金利低下のメリットを受けられる可能性がある | |
| 固定金利期間選択型のデメリット | |
| 固定金利期間終了時に、変動金利型のような1.25倍ルールがないので、金利が上昇している場合に返済額が急激に上がる可能性がある | |
| 金利タイプの再選択時に、優遇金利などが借入当初の優遇幅に比べて小さいか、ない場合がある |
固定金利期間選択型に向いている人とは
全期間固定金利型住宅ローンの特徴やメリット・デメリット
全期間固定金利型のメリット |
金利が固定されるため金利変動リスクを回避できる |
低金利時の借入れは長期にわたりその低金利のメリットを享受できるため、完済までの金利動向によっては最終的にほかの金利タイプと比べて総返済額が少なくなる可能性もある |
|
返済額や総返済額が確定するため、家計管理がしやすくなる |
|
全期間固定金利型のデメリット |
変動金利型や短期の固定金利期間選択型より通常は金利が高めとなる |
| 金利下降局面において、さらなる金利低下のメリットを享受できない |
全期間固定金利型に向いている人とは
住宅ローンの利息はどうやって計算されているの?

返済回数 |
毎月返済額 |
利息分 |
元金分 |
借入残高 |
当初借入 |
30,000,000円 |
|||
1回目 |
103,536円 |
37,500円 |
66,036円 |
29,933,964円 |
2回目 |
103,536円 |
37,417円 |
66,119円 |
29,867,845円 |
3回目 |
103,536円 |
37,334円 |
66,202円 |
29,801,643円 |
変動金利型の住宅ローンを徹底比較
| 金融機関 | 下限金利相場(優遇金利適用後) |
|---|---|
| 都市銀行(4社) | 0.345%~0.625% |
| ネット銀行(3社) | 0.344%~0.647% |
- 2025年3月時点、新規借入の場合。
- 変動金利型住宅ローンの最優遇金利が適用された場合の下限金利のレンジ。
- 最下限金利の適用には利用条件による場合があるため、各銀行のHPをご確認ください。
固定金利期間選択型の住宅ローンを徹底比較
| 金融機関 | 下限金利相場(優遇金利適用後) |
|---|---|
| 都市銀行(4社) | 1.610%~2.150% |
| ネット銀行(3社) | 1.553%~2.163% |
- 2025年3月時点、新規借入の場合。
- 固定金利期間(10年)選択型住宅ローンの最優遇金利が適用された場合の下限金利相場
- 最下限金利の適用には利用条件による場合があるため、各銀行のHPをご確認ください。
また一般的には短い固定金利期間のほうがより金利が低いものですが、金融機関の戦略などにより、たとえば5年固定よりも10年固定の金利を低く提供しているところもあります。これにより各金融機関がどの金利タイプや固定期間に力を入れているのかが見えてきます。
全期間固定金利型の住宅ローンを徹底比較
| 金融機関 | 下限金利相場(優遇金利適用後) |
|---|---|
| 都市銀行(4社) | 2.170%~2.910% |
| ネット銀行(3社) | 1.973%~2.926% |
- 2025年3月時点、新規借入の場合。
- 全期間固定金利型(35年)住宅ローンの最優遇金利が適用された場合の下限金利相場
- 最下限金利の適用には利用条件による場合があるため、各銀行のHPをご確認ください。
まとめ
ただし、借入時の金利だけで住宅ローンを選んでしまうのは早計です。
住宅ローン借入時の融資手数料等のコストや、繰り上げ返済や金利タイプ変更等の借入後の手続き方法なども比較検討したうえうで、自分のライフプランにあった住宅ローンを選びましょう。
執筆者:小山英斗
未来が見えるね研究所 代表
CFP®、1級FP技能士(資産設計提案業務)、住宅ローンアドバイザー、住宅建築コーディネーター
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行で住宅ローンをお申し込み
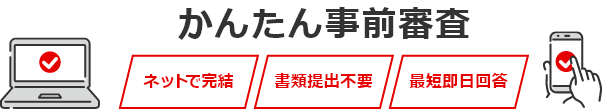

- 受付状況等により審査に日数がかかる場合があります