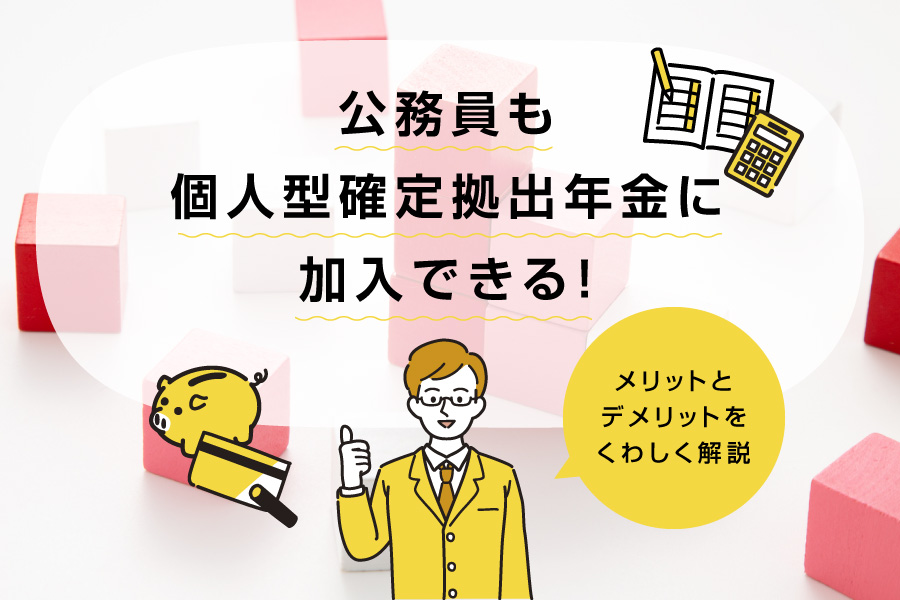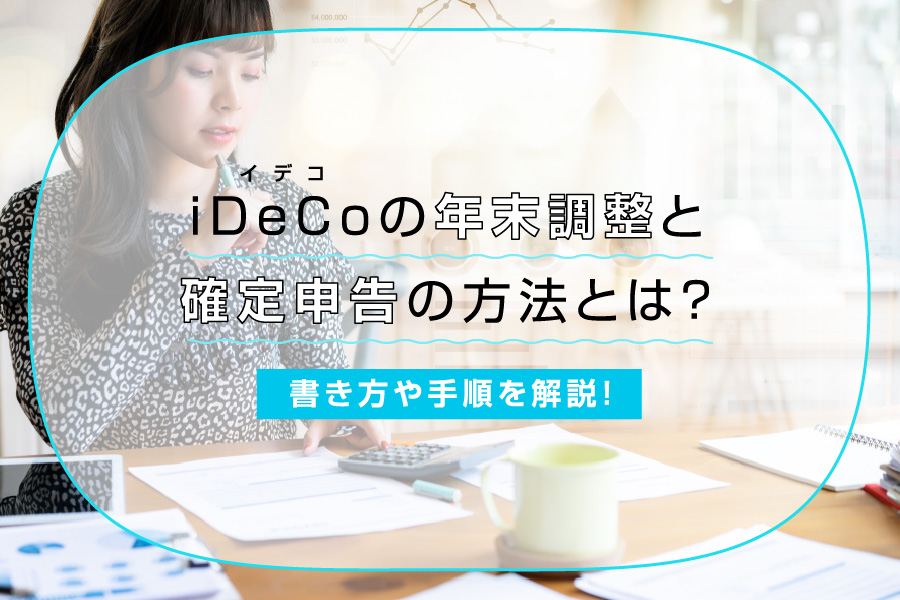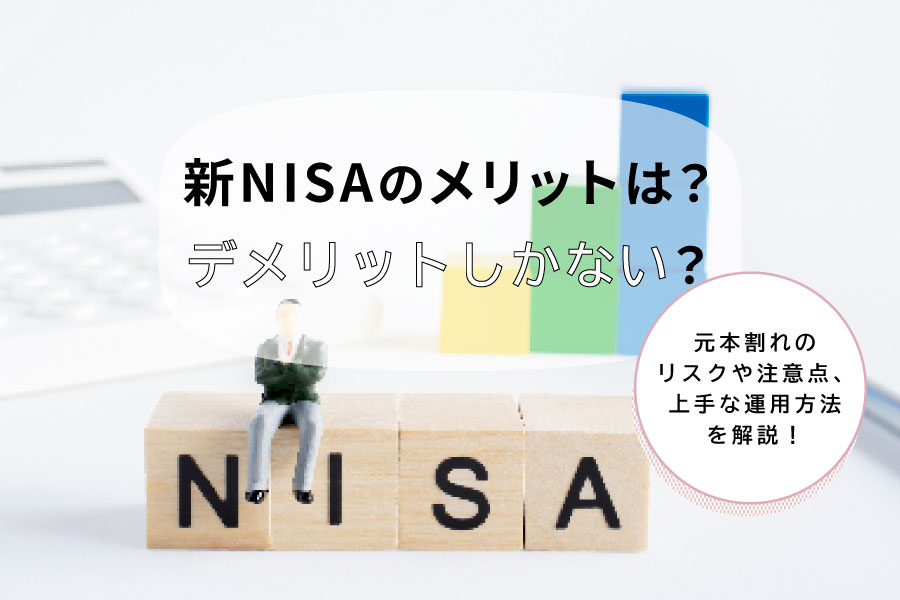【2025年版】iDeCo(イデコ)の所得控除はどのくらい?計算方法や税制優遇の効果を解説!
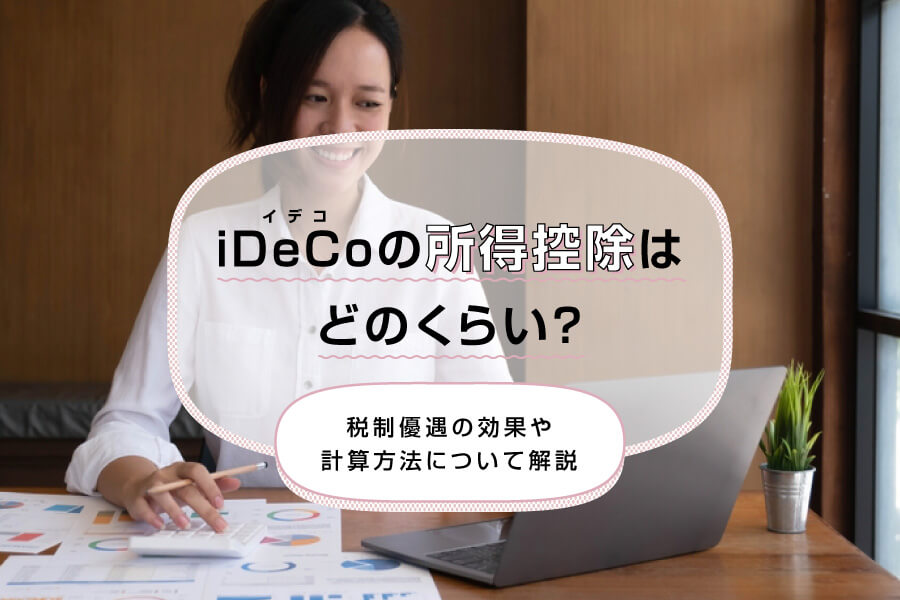
- 2025年11月26日
iDeCo(イデコ:個人型確定拠出年金)は、国が後押ししている私的年金制度です。
老後の生活資金を準備しやすいように、さまざまな税制優遇が用意されており、「掛金を全額所得控除できる」というのもそのひとつです。
この記事では、iDeCoの所得控除の効果について、シミュレーションを交えながら紹介していきます。
目次
iDeCoのメリット・3つの税制優遇とは?
まずは、iDeCoのメリットである税制優遇の詳細について紹介します。
iDeCoは3つのタイミングで税制優遇がある
iDeCoの大きなメリットとして、「加入によって3つの税制優遇が受けられること」が挙げられます。
- 掛金の積立時
- 掛金の運用時
- 資産の受取時
それぞれどのような税制優遇が受けられるのか、くわしく確認していきましょう。
1.掛金の積立時
iDeCoで拠出した毎月の掛金は、全額所得控除の対象となります。
たとえば、毎月2万円ずつ拠出する場合、年間24万円が課税所得から控除される仕組みです。
所得控除を受けることで、その年の所得税や翌年の住民税が軽減されるメリットがあります。
なお、所得控除の適用を受けるためには、確定申告や年末調整で手続きを行う必要があります。
手続きの詳細については、本記事内でもくわしく解説していますので、あわせて参考にしてください。
2.掛金の運用時
iDeCoへ加入後、拠出した掛金は投資信託や定期預金によって運用を行います。
通常、金融商品の運用で得た利益には20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかりますが、iDeCoでは非課税で運用成果を受け取ることが可能です。
利益確定をして他の金融商品へ切り替える際も税金が差し引かれないため、効率よく再投資できるメリットがあります。
3.資産の受取時
iDeCoで拠出した資金は、原則60歳以降に「年金」もしくは「一時金」で受け取ります。
また、「年金」と「一時金」を組み合わせて受け取る方法を選べるところもあります。運営管理機関によって異なりますので、ご希望の場合は、加入前に確認してみましょう。
年金で受け取る場合は「公的年金等控除」、一時金で受け取る場合は「退職所得控除」の対象となり、一定額まで非課税で受け取ることが可能です。
拠出時の所得控除だけでなく、将来の受取時にも所得控除が受けられるのは、iDeCo加入の大きなメリットといえます。
iDeCo所得控除の効果は?負担軽減額を知ろう
「iDeCoには税制メリットがある」という話を聞いて、加入を検討している人もいるかもしれません。
では、実際にiDeCo加入によってどれくらいの税負担が軽減されるのでしょうか。シミュレーションによって確認してみましょう。
課税所得で見る、所得税・住民税の負担軽減額
所得税や住民税は、「課税所得」の金額をもとに税額が決定されます。住民税は課税所得に対して一律10%ですが、所得税は課税所得の金額によって5%~45%までの税率が適用される仕組みです。
たとえば、課税所得が400万円の人を例に税負担の軽減額を算出してみましょう。「iDeCoに未加入の場合」と、「毎月20,000円の拠出をした場合」の税負担の差は次の通りです。
横スクロールして確認
| iDeCo未加入時 | iDeCo加入時 | 差額 | |
|---|---|---|---|
| 課税所得 | 4,000,000円 | 3,760,000円 | ▲240,000円 |
| 所得税(20%) | 714,500円 | 666,500円 | ▲48,000円 |
| 住民税(10%) | 400,000円 | 376,000円 | ▲24,000円 |
| 税額合計 | 1,114,500円 | 1,042,500円 | ▲72,000円 |
- 復興特別所得税は考慮していません
iDeCoに加入すると、年間の拠出額が全額所得控除の対象となります。このケースでは、年間24万円が課税所得から控除される計算です。
その結果、所得税と住民税の負担も軽減され、最終的に72,000円の税金が軽減されました。
仮に20年間拠出を続ければ、72,000円×20年間=144万円の税負担が軽減されることになり、長く拠出を続けるほどメリットも大きくなることが分かります。
iDeCoの所得控除メリットを課税所得別にシミュレーション
前述の通り、所得税には5%~45%の税率があり、課税所得が多くなるほど税率が高くなる仕組みです。
ここからは、税率別の所得控除メリットを確認してみましょう。
【毎月2万円の拠出をした場合】
| 課税所得 | 所得税率 | 住民税率 | 軽減額 |
|---|---|---|---|
| 195万円未満 | 5% | 10% | 36,000円 |
| 195万円以上330万円未満 | 10% | 48,000円 | |
| 330万円以上695万円未満 | 20% | 72,000円 | |
| 695万円以上900万円未満 | 23% | 79,200円 | |
| 900万円以上1,800万円未満 | 33% | 103,200円 | |
| 1,800万円以上4,000万円未満 | 40% | 120,000円 | |
| 4,000万円以上 | 45% | 132,000円 |
- 復興特別所得税は考慮していません
上記表から、同じ拠出金額であっても、税負担の軽減額に差があることが分かります。
毎月2万円を拠出した場合、所得税率が5%の人と45%の人では、年間96,000円もの差があり、課税所得が多い人の方がより恩恵を受けられる仕組みとなっています。
\初心者でもカンタンにはじめられる!/
職種によっては所得控除に使える金額の上限が異なる
「iDeCoは掛金が全額所得控除になる」と聞くと、「税負担軽減のために、たくさん積み立てをしたい!」と思うかもしれません。
しかし、毎月の拠出額は職種ごとに上限が定められており、それ以上は積み立てができないようになっています。
iDeCoに加入する際は、自分の上限額を確認して毎月の拠出額を決定しましょう。
横スクロールして確認
| 対象 | 企業年金等(*1)への加入 | 月額/年額の上限 |
|---|---|---|
| 自営業者等 | - | 68,000円/816,000円(*2) |
| 会社員・公務員等 | あり | 20,000円(*3) |
| なし | 23,000円/276,000円 | |
| 専業主婦(夫) | - | 23,000円/276,000円 |
- 企業型確定拠出年金、確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員制度のことを指します
- 国民年金基金の掛金または国民年金の付加保険料との合算した金額です
- 下記条件があります
会社員・公務員等の第2号被保険者が確定給付型の他制度(*1)とiDeCoを併用する場合、iDeCoの拠出限度額は2万円です。ただし、各月の企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額と合算して月額5.5万円が上限です。 式で表すと以下のようになります。
iDeCoの拠出限度額(上限2万円)=月額5.5万円 ー(各月の企業型DCの事業主掛金額+他制度掛金相当額)
そのため、企業型DCの事業主掛金と他制度掛金相当額が高い場合、iDeCoの拠出限度額が減少または拠出できなくなることがあります。
また、以下の加入条件があります。
また、以下の加入条件があります。
- 企業型DC・iDeCoの掛金が年単位拠出でないこと
- マッチング拠出を利用していないこと
- 拠出額が上限内であること
また、2022年10月の制度改正により、これまで加入できなかった企業型確定拠出年金の加入者もiDeCoに原則加入できるようになりました。
加入要件の年齢も65歳まで延長されたため、これまで加入を諦めていた人も、この機会に加入を検討してみるとよいでしょう。
職種別の所得税・住民税負担軽減額シミュレーション
前述の通り、iDeCoの掛金の上限額は職種によって異なります。そのため、課税所得が同じ水準であっても、受けられる税制優遇に差が生まれることとなります。
ここでは、課税所得が同じ400万円の会社員と自営業者について、税負担の軽減額を比較してみましょう。
企業年金がない会社員の場合は年間上限が276,000円、自営業者は816,000円となり、それぞれ上限まで利用したとします。
【課税所得400万円(所得税率20%)、掛金上限まで利用した場合】
横スクロールして確認
| 会社員(企業年金がない) | 自営業者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 所得税軽減額 | 住民税軽減額 | 所得税軽減額 | 住民税軽減額 | |
| 1年 | 55,200円 | 27,600円 | 163,200円 | 81,600円 |
| 5年 | 276,000円 | 138,000円 | 816,000円 | 408,000円 |
| 10年 | 552,000円 | 276,000円 | 1,632,000円 | 816,000円 |
| 20年 | 1,104,000円 | 552,000円 | 3,264,000円 | 1,632,000円 |
- 復興特別所得税は考慮していません
所得税軽減額と住民税軽減額を足して1年間の軽減額は、会社員が82,800円、自営業者が244,800円なので、会社員と自営業者の軽減額の差額は1年間で162,000円になり、利用期間が長くなるほど差が大きくなっていきます。
自営業者は、会社員に比べて掛金の上限額が大きいため、より多くの税制優遇を受けられるというメリットがあります。
iDeCoによる所得控除の注意点
iDeCoによる所得控除を受ける際は、次の2つの点に注意が必要です。
- 軽減される税金は本来納める税額が上限となる
- 専業主婦(主夫)の場合は所得控除の効果が少ない
それぞれくわしく確認していきましょう。
軽減される税金は本来納める税金が上限となる
iDeCoの大きなメリットは、「所得税や住民税が軽減されること」です。
ただし、ここで注意したいのが、「軽減される範囲は、本来納める税金の額まで」という点です。
たとえば、iDeCoによる税制メリットが10万円であったとしても、納める税金が7万円であれば、軽減額は7万円となります。
差額の3万円分が還付されるわけではありませんので、正しく理解しておきましょう。
専業主婦(主夫)の場合は所得控除の効果が少ない
iDeCoは、専業主婦(主夫)でも月額23,000円を上限に加入ができます。
掛金は全額所得控除できますが、専業主婦(主夫)で収入がない場合はそもそも所得税がかからないため、iDeCoによる所得控除の効果は少ないといえます。
ただし、「運用益が非課税になる点」や、「受取時に所得控除が使える点」は、専業主婦(主夫)にとっても大きなメリットです。
特に、専業主婦(主夫)の場合は、一般的に退職金がなく、受給できる公的年金も少ないため、課税されることなくiDeCoの掛金を受給できる可能性があります。
専業主婦(主夫)の方も将来の備えの一環として、iDeCoの加入を検討するとよいでしょう。
iDeCoの所得控除を受けるには手続きが必要
iDeCoの加入後、所得控除を適用してもらうためには、一定の手続きを行う必要があります。
「会社員・公務員」と「個人事業主・フリーランス」に分けて手続きを確認していきましょう。
会社員や公務員は「小規模企業共済等掛金控除証明書」で年末調整
- 郵送される「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管する
- 会社から渡された「給与所得者の保険料控除申告書」に記入する
- 払込証明書を添付して会社に申告書を提出する
iDeCoへ加入後、国民年金基金連合会から毎年10月に「小規模企業共済等掛金払込証明書」が送付されます。
その後、勤務先から受け取る年末調整の書類(給与所得者の保険料控除申告書)に、その年に支払ったiDeCoの掛金の合計額を記入してください。
なお、払込証明書は年末調整の書類に添付して提出しますので、大切に保管しておきましょう。
年末調整とは
年末調整とは、会社員など、給与から天引きで税金を納めている人が、その年に納付する所得税と復興特別所得税を精算する手続きのことです。
毎月、給与から天引きされる税額は、iDeCoの所得控除や生命保険料控除といった控除額は考慮されていません。
そのため、年間の給与が確定する年末時期に、年末調整を行い、控除額を含めた税額を再計算する仕組みです。
個人事業主やフリーランスを含む自営業者は確定申告で手続き
- 「小規模企業共済等掛金払込証明書」を保管する
- 確定申告の申告書に記入する
- 払込証明書を添付して税務署に申告書を提出する
個人事業主やフリーランスの場合は、確定申告によって所得控除の適用を受けます。
また、会社員で年末調整をしていない人や、年末調整までに払込証明書が届かなかった人も確定申告の対象となります。
確定申告を行う場合は、国民年金基金連合会から送付された「小規模企業共済等掛金払込証明書」に基づいて、確定申告書へ払込金額を記入してください。
払込証明書は申告書に添付して税務署へ提出しますが、電子申告の場合は添付を省略することもできます。ただし、その場合も5年間は保管が必要です。
なお、筆者は確定申告によってiDeCoの所得控除を受けていますが、所定の記入欄に金額を入力するだけですので、それほど手間がかかる作業ではありません。
証明書を受け取ってから確定申告を行うまでに少し時間が空きますので、きちんと証明書を保管しておくように注意しましょう。
所得税や住民税はいつ・どのように還付される?
iDeCoの所得控除を利用すると、所得税と住民税が軽減されます。しかし、いつどのように軽減を受けられるかは税金の種類によって異なります。
ここからは、所得税と住民税が軽減される方法・タイミングについて確認していきましょう。
所得税は現金で還付される
iDeCoの所得控除によって還付される所得税は、現金で還付されます。
年末調整の場合は、勤務先の手続きにもよりますが、12月か1月の給与とともに還付されることが一般的です。
その他に、別途振込を行う方法や現金を手渡しする方法もあるため、詳細は勤務先へ確認するとよいでしょう。
また、確定申告を行った場合は、おおむね1ヵ月から1ヵ月半程度で指定口座へと還付金が入金されます(電子申告によって申告した場合は3週間程度)。
住民税は還付ではなく翌年分が軽減される
一方、住民税は現金の還付ではなく、翌年の住民税が軽減される形で優遇を受けます。
たとえば、課税所得が300万円で、iDeCoの年間拠出額が24万円であった場合、課税所得が276万円となり住民税が軽減される仕組みです。
会社員や公務員の場合は、給与からの天引きによって住民税を納めているため、どれくらいの税金が軽減されたのか実感しにくいかもしれません。
実際の軽減メリットを確認したい場合は、昨年の給与明細と見比べてみるとよいでしょう。
また、自営業者の場合は、翌年6月以降に住民税の納付書が送付されます。
こちらもすでに軽減された税額が記載されているため、メリットが分かりにくいかもしれません。昨年の納付書と見比べてみると、軽減額が実感できるでしょう。
まとめ
iDeCoは老後の年金を私的に準備する制度で、さまざまな税制優遇を受けられることが大きなメリットです。
毎月どれくらいの掛金を拠出できるかは職種によって異なりますので、ご自身の上限額を確認したうえで加入を検討しましょう。
また、iDeCoで所得控除を受けるためには、年末調整や確定申告による手続きが必要です。加入後は毎年忘れずに手続きを行いましょう。
執筆者:椿 慧理(つばき えり)
執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格、内部管理責任者
執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士、一種外務員資格、内部管理責任者
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行でiDeCoを始める方法
あわせて読みたい
ご注意事項
iDeCoをお申し込みいただく前に、下記についてご確認ください。
- 原則、60歳まで引き出し(中途解約)ができません
- 脱退一時金を受け取れるのは一定の要件を満たす方に限られます。
- ご本人の判断で商品を選択し運用する自己責任の年金制度です
- 確定拠出年金制度では、ご加入されるご本人が自らのご判断で、商品を選択し運用を行いますので、運用結果によっては受取額が掛金総額を下回ることがあります。
- 当行から特定の運用商品の推奨はできません。
- 運用商品の主なリスクについて
- 預金は元本確保型の確定利回り商品です。預金は預金保険制度の対象となります。
- 当行のiDeCoで取り扱う保険は元本確保型商品です。ただし、運用商品を変更する目的で積立金を取り崩す場合は、市中金利と残存年数等に応じて解約控除が適用されるため、結果として受取金額が元本を下回る場合があります。
- 投資信託は価格変動商品です。預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。運用実績は市場環境等により変動し、元本保証はありません。また、当行でお取り扱いする投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
- 預金、保険および投資信託は異なる商品であり、それぞれリスクの種類や大きさは異なります。
- 初回手続き時、運用時、給付時等で、各種手数料がかかります
- iDeCoには、初回手続き手数料・毎月の事務手数料・資産管理手数料・運営管理機関手数料・給付事務手数料等がかかります。
- 手数料は、加入者となられる方は毎月の掛金から、運用指図者となられる方は積立金から控除されます。年金でお受け取りになられる方は給付額から控除されます。
- 60歳になっても受け取れない場合があります
- 50歳以上60歳未満で加入した場合等、60歳時点で通算加入者等期間(*)が10年に満たない場合は、受給可能年齢が引き上げられます。
- 60歳以上で新規加入した場合、加入から5年経過後に受給可能となります。
- 通算加入者等期間は、iDeCoおよび企業型DCにおける加入者・運用指図者の期間の合算となります。
株式会社 三菱UFJ銀行
(2026年2月5日現在)