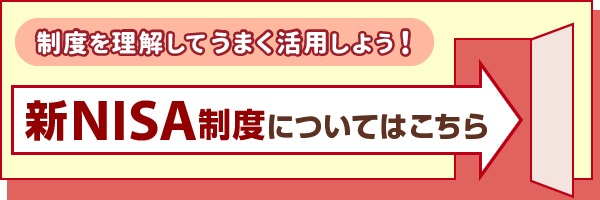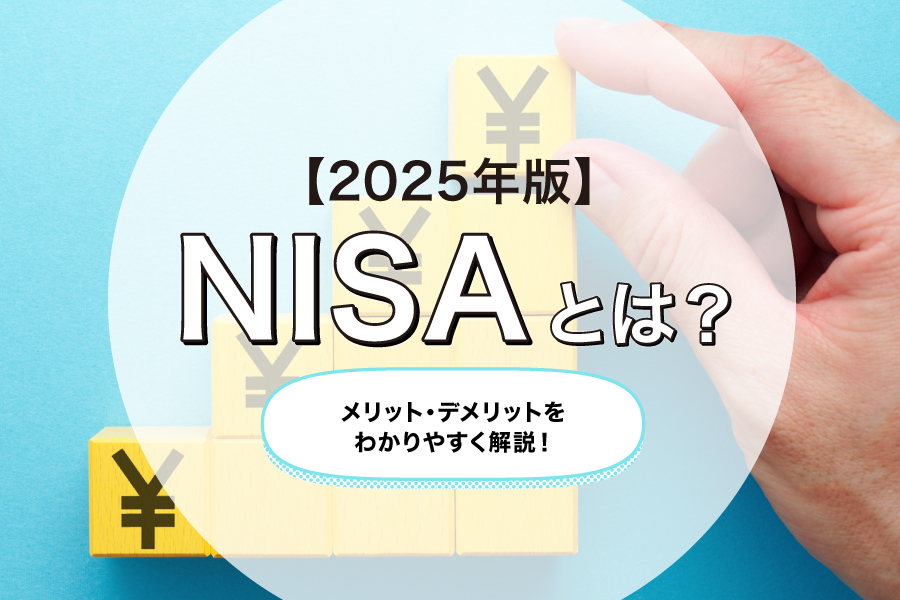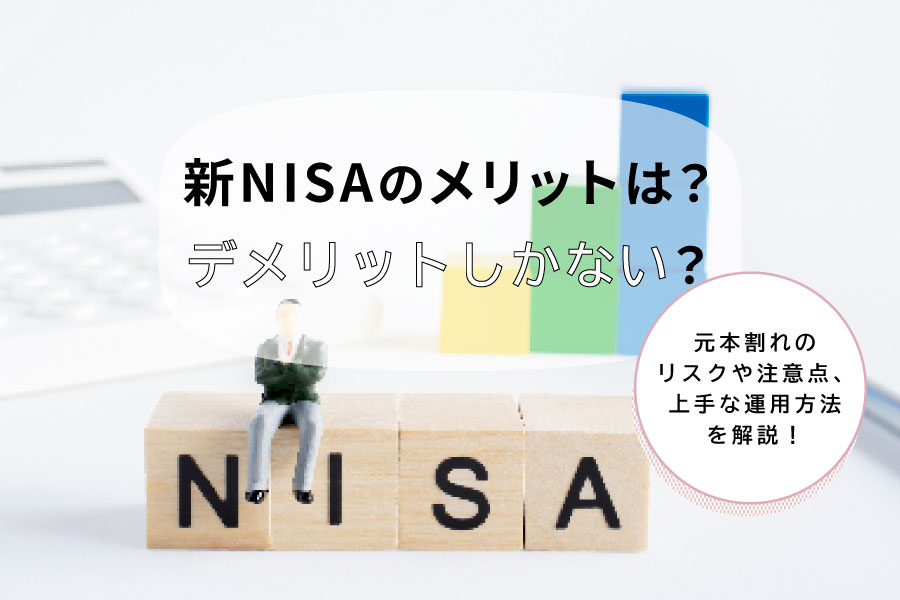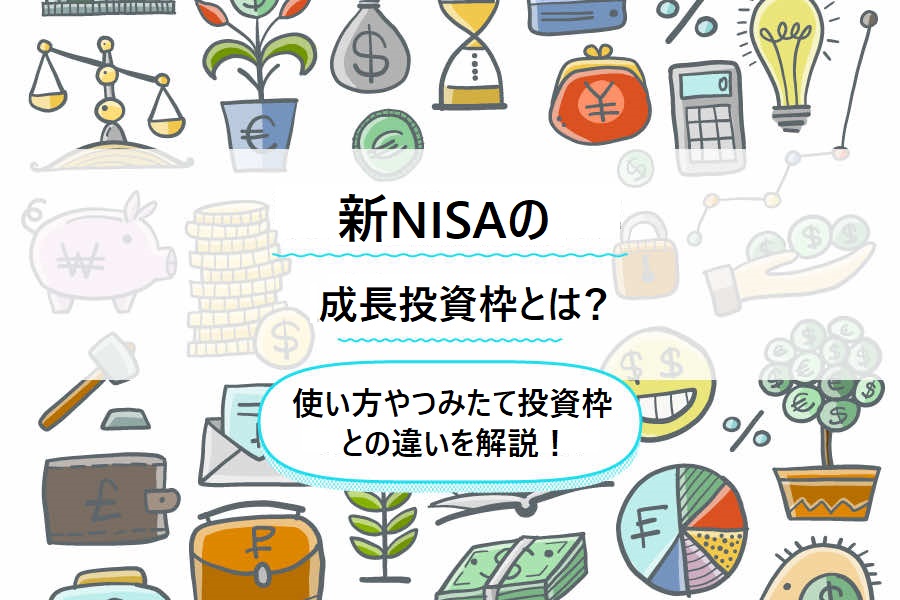つみたてNISA(積立NISA)にデメリットはある?NISAとの比較や向いている人をFPが解説!
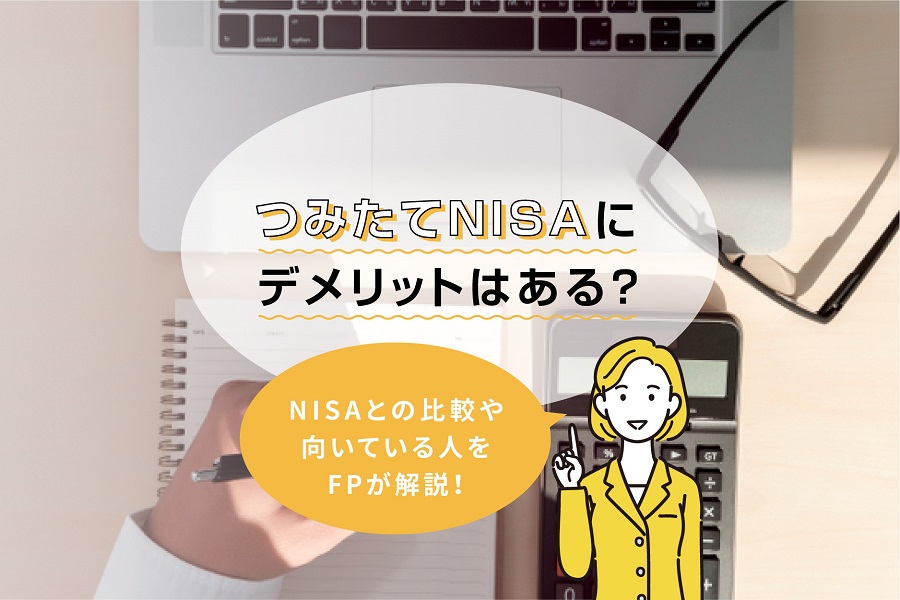
- 2022年4月20日
- 2023年12月29日
投資初心者でもチャレンジしやすい仕組みが多く盛り込まれていますが、利用する人によってはデメリットがあることも理解しておくのが大切です。
この記事では、つみたてNISAがかかえるデメリットやメリット、つみたてNISAをおススメしたい人をわかりやすく解説します。
- 現行制度は、2024年1月以降に制度内容が大きく改正される予定です。
本ページは2022年12月16日(金)「令和5年度の税制改正大綱」で公表された情報をもとに作成しております。今後変更となる可能性もございますので、あらかじめご了承ください。
つみたてNISAとはどんな制度?
つみたてNISAは、長期投資を通じた資産形成を促す金融庁が主導する制度です。
一般的な投資と比べて得をしやすい制度と言われていますが、具体的にどのような制度なのでしょうか。
つみたてNISA(少額投資非課税制度)とは
つみたてNISAは、2018年1月からスタートした少額投資非課税制度です。
つみたてNISAの対象商品は、長期の積み立て・分散投資に適した投資信託と上場株式投資信託(ETF)だけです。
これは一定の基準を満たした安全性が高い商品に限定し、あらゆる年代の投資初心者が投資に取り組みやすい環境を作るためとされています。
現行制度ではつみたてNISAの年間非課税枠は40万円であり、つみたてNISAで購入した商品から得られた利益(分配金・売却益)が非課税となります。
非課税保有期間は購入した年を含め20年間です。
非課税期間は年ごとに定められており、2022年に購入した金融商品は2041年まで、2023年に購入した金融商品は2042年まで運用益に税金がかかりません。
つみたてNISAとNISAの違い
つみたてNISAはNISA(少額投資非課税制度)の一部です。
NISAはつみたてNISAとNISA(一般NISA)の2種類からいずれかを選ぶことができます。
同時に両方の制度を利用することはできませんが、年ごとにつみたてNISAと一般NISAの切り替えが可能です。
変更したい年の非課税投資枠を使用していなければ、当年中に切り替えを行えます。
NISAは2014年1月からスタートした少額投資非課税制度です。
NISAには年間120万円までの非課税枠があり、上場株式やETF、投資信託、REITなどさまざまな金融商品を選択できます。
非課税期間は5年間とつみたてNISAより短期間に設定されているため、積極的な運用を望む人に向いている制度といえます。
また、NISA・つみたてNISAは18歳以上の成年だけが利用できる制度ですが、未成年を対象としたジュニアNISAという制度があります。
ジュニアNISAで非課税となる金融商品はNISAと同じですが、年間の非課税枠は80万円までと少額になっています。
またNISAにはない払い出し制限が設けられており、18歳になるまでは原則として払い出すことができません。
つみたてNISAとNISAの違い、2024年以降の新NISA制度の概要は以下の表をご覧ください。
- 2023年までのつみたてNISA・NISAの違い
| つみたてNISA | NISA | |
|---|---|---|
| 利用できる方 | 日本在住の18歳以上 | |
| 非課税保有期間 | 20年間 | 5年間 |
| 年間非課税枠 | 40万円 | 120万円 |
| 非課税保有限度額 | 800万円 | 600万円 |
| 投資対象 | 金融庁への届出を済ませた投資信託・ETF | 上場株式・投資信託・ETF・REITなど |
| 買付方法 | 積立投資 | 通常の買付・積立投資 |
| 投資可能期間 | 2042年まで ※制度改正により2023年まで |
2028年まで ※制度改正により2023年まで |
| ロールオーバー | 不可 | 可 |
| 備考 | 併用不可、年単位で一方を選択可能 現行制度は2023年中まで |
|
- 2024年以降のNISA制度の概要
| NISA | ||
|---|---|---|
| 勘定の呼称 | つみたて投資枠 ※従来のつみたてNISA |
成長投資枠 ※従来の一般NISA |
| 利用できる方 | 日本在住の18歳以上 | |
| 非課税保有期間 | 無期限 | |
| 年間非課税枠 | 120万円 | 240万円 |
| 非課税保有限度額 | 合計1,800万円 ※内成長投資枠は1,200万円以内 |
|
| 投資対象 | 金融庁への届出を済ませた投資信託・ETF ※従来のつみたてNISAと同じ |
上場株式・投資信託・ETF・REITなど ※高レバレッジ型、毎月分配型の投資信託など一部除外 |
| 買付方法 | 積立投資 | 通常の買付・積立投資 |
| 投資可能期間 | 無期限 | |
| ロールオーバー | 不可 | 不可 ※課税口座に払い出しされるが、非課税期間に得た運用益に対しては非課税 |
| 備考 | つみたて投資枠と成長投資枠は併用可 | |
投資信託と主な商品
| 概要 | つみたてNISA | NISA | |
|---|---|---|---|
| 株式 | 株式会社が事業資金を調達するために発行する有価証券 | × | ○ |
| ETF | 株価や指数への連動をめざす投資信託。株式市場に上場されている | ○ ※対象は金融庁が指定 |
○ |
| 債券 | 企業や国などが資金を借り入れるために発行する有価証券 | × | ○ |
| REIT | 集めた資金で不動産を運用し利益を分配する金融商品 | × | ○ |
投資信託は、多くの投資家から集めた資金をひとつにまとめ、運用会社が株式などを売買・運用して得た利益を投資家に分配する金融商品です。
投資対象によって「株式100%型」「複合資産型(バランス型)」に分類されています。
株式100%型は株式への投資のみを行います。投資対象の株価が上昇すれば大きなリターンが望める一方、株価が下落すると価値が下がるリスクが高い商品です。
複合資産型(バランス型)は株式、債券、REITなど、値動きが異なる商品に分散して投資を行うため、安定的な運用をすることができます。
ETFは投資信託の一種で、集めた資金を運用し株価指数等への連動をめざす金融商品です。
株式市場に上場されており、1日1回算出される基準価格で売買する投資信託とは異なり、リアルタイムで変動する市場価格での売買で利益を得ることができます。
債券は国や企業などが発行する有価証券で、投資家から資金を調達することを目的としています。
国や企業がお金を借りるために発行する有価証券であり、発行する時点で返済日である償還期限や利率が決められているため、購入する時点で償還期限までに受け取れる利益が確定します。
REITは集めた資金で不動産への投資を行い、賃貸収入や売買収入を投資家に配当する金融商品です。
不動産投資信託と呼ばれ、株式市場で取引を行えます。
ロールオーバーとは
ロールオーバーとは、NISAで利用できる非課税期間の延長方法です。
つみたてNISAの非課税期間満了後は、売却または課税口座への移し替えといった選択肢しかありません。
しかしNISAは5年間の非課税期間が終了した商品を、翌年の非課税枠に移し替えて非課税期間を延長することができます。
なお、2019年以降にNISAで購入した残高は、2024年から始まる新制度のNISAへロールオーバーすることはできません。
一方で、2023年以前のNISAの残高は新制度NISAの非課税保有限度額である1,800万円には算入されません。
そのため、2023年につみたてNISAを開始すると、新制度NISAを合わせて最大1,840万円の非課税投資残高を保有することが可能です。
三菱UFJ銀行のNISA・つみたてNISA
三菱UFJ銀行のNISA・つみたてNISA
つみたてNISAのデメリット6選
つみたてNISAは、初心者でも資産形成の入り口として利用できる魅力的な制度として、2022年9月末時点で466万口座を超えています。
魅力的な制度であるつみたてNISAですが、始める前にはデメリットを理解することも必要です。
(1) 元本割れのリスクがある
幅広い金融商品から投資先を選べるNISAに対し、つみたてNISAで選べる金融商品は、金融庁指定の投資信託に限られます。
ただし過去の市場を振り返れば、新型コロナウイルスなどを引き金にした金融危機により落ち込むことはあっても、長期的には世界の市場は右肩上がりで成長を続けてきました。
新たなNISA制度では、非課税保有期間が無期限になることから、現行のNISA制度で起こり得た「非課税期間満了時まで運用を続けたものの、相場が悪く含み損を抱えてしまう」といったケースは避けられます。
非課税保有期間を気にせずに運用できるようになるため、手堅く利益を得やすくなると考えられます。
(2) 損益通算、繰越ができない
NISAおよびつみたてNISA共通のデメリットとして、NISA口座で運用した商品から出た損失は、他の利益との相殺(損益通算)や繰り越しはできません。
通常の課税口座では、ある商品で発生した損失を、同じ口座内で運用する他の商品の利益と相殺し、課税対象となる所得を抑えることができます。
また、確定申告をすることにより、他の金融機関の証券口座の利益との相殺や、その損失を翌年以降3年間の利益と相殺する繰越控除の適用を受けることができます。
一方で、NISAはそもそも利益に対しての課税がされないので、上記のような損益通算や繰越控除の適用を受けることができません。
(3) 投資できる金融商品に限りがある
つみたてNISAは投資できる商品は金融庁指定の投資信託となります。
そのため、「株主優待目的で株式投資したい」「分配金の高いREITに投資したい」と考えたときに投資することはできません。
株式などに投資したい場合には、対象商品が幅広いNISA口座にする必要があります。
NISAは1人1口座しか開設できないため、つみたてNISA口座を開設していると、NISAを開設することができません。
(4) 非課税投資枠の月の上限金額がNISAと比較すると少ない
上述したように、現行制度ではつみたてNISAは年間の投資金額が40万円までと決まっており、それ以上投資することはできません。
年間120万円まで投資できるNISAと比べると投資額が3分の1程度であり、資金がある人は物足りなさを感じてしまうかもしれません。
資金に余裕がある方は、NISAでつみたてを検討してみても良いでしょう。
(5) 一括投資できない
投資信託の価格が低い時期にまとまった資金を投入したいと思っても、年間40万円の枠に一括投資することはできません。
そのため、相場のタイミングを見て一括で購入するような投資をしたい場合は、一般NISAで購入する必要があります。
ただし、2024年からのNISA制度ではつみたて投資枠と成長投資枠の併用ができるため、定期積立とタイミングを図った一括での金融商品の購入を両立させることが可能です。
(6) 金融機関の変更には時間がかかる
つみたてNISAおよびNISAは、一つの金融機関でのみ運用が可能です。
金融機関を変更する場合は、すでに開設しているNISA口座を廃止する必要があります。
NISA口座を廃止した金融機関から受け取った廃止通知書を、変更先の金融機関に提出することで、新たなにNISA口座を開設できます。
ちなみに廃止したNISA口座で新たに投資することはできませんが、そのときすでに投資していた口座にある資産は非課税期間が満了するまでは非課税で運用できます。
つみたてNISAは投資上限額が低めに設定された積立専用の制度であるため、自由度の高い資産運用には向きません。
また比較的安全性が高い金融商品が対象ではありますが、元本割れのリスクもあります。
一方で、つみたてNISAには定期的かつ長期の積立による資産形成をするための多くのメリットが設けられています。
次に紹介するつみたてNISAのメリットを見ていきましょう。
つみたてNISAのメリット5選
つみたてNISAには自由度の低さにまつわるデメリットがある一方、多くのメリットも存在します。
上手に活用すれば資産形成に大きく貢献してくれますので、特長を把握したうえでつみたてNISAを使った投資を行いましょう。
(1) 少額から始めることができる
投資信託は、多くの投資家から集めた資金を大きなまとまりにして運用する金融商品です。
株式や債券には購入できる金額の単位となる最低投資単位があり、大きな金額が必要になることが多いですが、投資信託は自分の好きな金額で購入することができます。
特につみたてNISAは一般的に毎月1,000円から積立することが可能なので、投資初心者でも安心して始められます。
(2) 商品選択が容易で初心者でも利用しやすい
つみたてNISAは、投資できる商品が、金融庁指定の投資信託で積立による投資に限定されています。
金融庁指定の銘柄は、購入時手数料0円など長期積立投資に適した投資信託に厳選されているので、初心者の方でも銘柄を選びやすくなっています。
また、投資信託は、1つの銘柄に集中せず複数銘柄に投資します。
個別銘柄への投資では1銘柄が大きく値下がりしてしまうと資産が大きく値下がりしますが、複数銘柄に分散投資しているのでその影響は小さくなり、初心者の方でもカンタンに分散投資が可能です。
つみたてNISA口座を開設後、投資信託を指定の銘柄から選び、毎月買付する金額を指定するだけです。
あとは自動的に毎月口座から引き落としとなり、指定通りに買付されます。最初の設定を行えば、その後は都度購入手続きをする必要はありません。
(3) 時間分散でリスクを抑えられる
つみたてNISAを活用した積立投資は、時間分散によるリスクの低減を狙えます。
正確な予測をしづらい値動きをする金融商品を、長期間にわたってタイミングを分散して購入することで、平均購入単価を抑えることができます。
ドル・コスト平均法とは
ドル・コスト平均法は、価格が変動する金融商品を長期間に渡り、同じ金額で購入し続ける手法です。
毎月1万円ずつ投資信託の積立を行う場合、ドル・コスト平均法では1口あたり100円の時には100口、200円では50口購入することになります。
安いタイミングでは購入する口数がふえるため、将来値上がりしたときには多くの利益が望めます。
一方で高値のタイミングでは少ない口数に留まるため、今後単価が下がったときの影響を少なくすることができます。
ドル・コスト平均法で長期運用すれば、購入単価を平準化して運用リスクを低減できます。
(4) 購入時手数料は無料、運用中のコストも低コスト
投資信託は保有期間中に運用管理費用がかかるため、長期になるほどそのコストはかさみます。
投資信託の購入時にかかる購入手数料や、保有期間中に発生し続ける運用管理費用などにより、運用益がなくなってしまう可能性もあります。
また、運用管理費用が低コストの投資信託に限定されていることから、どの銘柄を選択しても低コストで長期運用が可能です。
(5) いつでも売却可能
つみたてNISAは、売却タイミングの制限がありません。資金に余裕がないときはいつでも積立を停止することができ、運用されている投資信託はいつでも売却可能です。
ただ、購入時より売却価格が下がっていると損をするため、積立を停止して売却は利益がでるまで待つこともできます。
つみたてNISAで効果的に資産運用するためのポイント
つみたてNISAは、最初の設定だけ行ったあとは細かく手を入れる必要のない運用方法です。
効果的に利益を得るためにも、以下の点に注意をした運用を心掛けましょう。
すぐに売却せずコツコツ続ける
つみたてNISAにおける成功の秘訣は、コツコツと投資をし続けることです。
投資信託商品も投資の一種であるため、一時的に値上がりをすることも値下がることもあります。
実際に自分が保有している投資信託が大きく値下がると、不安になり他の商品へ乗り換えしたくなるかもしれません。
また、値上がったタイミングで利益を確定するために売却したくなる人もいるでしょう。
つみたてNISAで積み立てる投資信託は、自動的に運用益が元本にプラスされ再投資されます。これにより、運用益から運用益が生み出される複利効果を期待することができます。
長期間投資し続けるほど複利効果で運用益は膨らみ続けていきますので、コツコツ続けることが大きな利益に繋がります。
自分に合った金融期間と商品を見極める
つみたてNISAで効果的な運用をするには、自分に合った金融機関と投資商品の選択が大切です。
つみたてNISAで投資できる商品は約200種類ありますが、すべての金融機関がすべての商品を扱っているわけではありません。
金融機関ごとに扱う商品の種類や本数は異なるため、自分が普段使っている金融機関がお目当ての商品を扱っていない場合もあります。
また、一度に投資できる最低金額の設定や自動引落しできる銀行口座の種類など、金融機関によって取り決めはさまざまです。
まずは自分が利用したいつみたてNISAのサービスを行っている金融機関を探すのがおススメです。
つみたてNISAで投資できる投資信託も、投資対象の国や業界、組み入れ銘柄の種類や運用方針など、商品の個性は豊かです。
そのなかから自分が投資したい投資信託商品を見つけても、お目当ての金融機関で扱っていない場合があります。
FPが解説!つみたてNISAはこんな人におススメ
一般的な投資信託への投資に比べ、多くのメリットを持つつみたてNISAは、どのような人におススメできる制度なのでしょうか。
ここではファイナシャルプランナーの視点から、つみたてNISAをおススメしたい人をご紹介します。
これから投資を始めたい人
- 投資に興味はあるけれど、始める機会がなかった人
- 投資商品や銘柄の種類などの知識がない人
つみたてNISAは、これまで投資に関心がなかった人でも投資に参入しやすいように設けられた制度です。
投資は制度が複雑なうえ、商品は何千という種類があるため、最初の選び方がわからないという人も多いでしょう。
つみたてNISAで選べる商品は、金融庁が定めた基準を満たした約200種類に絞られていますので、銘柄に関する知識が少ない投資初心者の方にも選びやすくなっています。
また、つみたてNISAで選べる商品は全て購入時手数料が無料です。
さらに、つみたてNISAで選べる商品の多くを占めるインデックス型投資信託は、保有期間中に支払い続ける信託報酬の額が低く設定されている傾向にあります。
これまで投資に触れてこなかった人、投資商品の知識がない人にとっては、選び方とコストの面からも安心して挑戦しやすい制度といえます。
毎月3万円程度の積立投資をしたい人
- あまり多くの資金を投資に回せない人
- 少額から少しずつ投資を始めてみたい人
つみたてNISAは、毎月3万程度の積立投資をしたい人におススメしたい制度です。
つみたてNISAの非課税投資枠は、毎年40万円が上限とされています。
1カ月あたりに分割すると、約33,000円です。
貯蓄を目的に、なんとなく1万円~3万円程度を定期預金や他の銀行の普通預金にうつして積立をしている方も多いのではないでしょうか。
しかし、残念ながら現在の銀行の預金の金利は0.001%程度と低く、利息を期待できない現状です。
積立方法をつみたてNISAに変更すれば、相場によって変動はあるものの長期で見れば預金以上の値上がりを期待することができます。
また、1回設定すれば自分でお金を移動する手間も省くことができるので貯蓄のし忘れ防止にもなります。
毎月3万円程度の投資で効率良く利益を出したい方にとっては、ぜひ利用していただきたい制度です。
じっくりと将来に備えたい人
- 老後に向けた資産を作りたい人
- 長期積立投資のメリットを活かしたい人
つみたてNISAの大きなメリットは、運用益が20年間非課税になることです。
NISAに比べて非課税の期間が長いので、長期的な目線で運用を検討することができます。
投資は運用する期間が長くなるほど、1年あたりの収益の振れ幅が安定的なものになります。
また、先述したように長期投資は運用益を元本にプラスして、さらに利益を生む複利効果や、積立で投資時期を分けることで平均購入単価も安定させる効果が期待できますので、長期積立投資のメリットを活かしながら、じっくりと将来に向けて備えたい人にとっておススメな制度です。
60歳前の急な出費にも備えたい人
- 大きな出費に備える貯蓄と投資を両立させたい人
- iDeCoを始める前に投資信託を購入する練習をしたい人
つみたてNISAで積み立てた商品は、20年の非課税期間中でもいつでも売却することができます。
運用益が非課税になる制度に「iDeCo」があります。
iDeCoは「個人型確定拠出年金」であるため、原則として積み立てたお金は60歳になるまで引き出せません。
お金に鍵をかけるという点ではメリットですが、余剰資金を全てiDeCoで積み立てた結果、大きな出費に対応できなくなるおそれがあります。
一方のつみたてNISAは好きなタイミングで売却できるため、急な入り用にも柔軟に対応できます。
60歳になる前に大きな出費が考えられる人は、つみたてNISAでの運用を優先して考えるとよいでしょう。
また、老後への備えとしてiDeCoを検討している人が、投資信託に慣れるためにつみたてNISAからスタートするのもよい選択です。
まとめ
つみたてNISAは投資できる金融商品の制限や損益通算不可、投資可能額が年間40万円に限定されるなど、いくつかのデメリットがある制度です。
一方で、商品の選びやすさや運用益が20年間非課税になるなどのメリットも多く、初心者から投信経験者まで幅広い層が利用しやすい制度となっています。
メリット・デメリットを踏まえ、自分に適した投資ができるようつみたてNISAの利用を検討しましょう。
執筆者保有資格:2級ファイナンシャル・プランニング技能士
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
三菱UFJ銀行でつみたてNISAを始める方法
インターネットバンキングなら窓口に行く必要がないため、
24時間365日お取引ができます。
- 他金融機関で2018年以降のNISA口座を既に開設しているお客さまは、金融機関変更のお手続きが必要です。廃止通知書の提出を伴うNISA口座開設のお手続きは、店頭のみでのお取り扱いとなります(三菱UFJダイレクトではお申し込みいただけません)。ご来店の際は、お手数ですが「ご来店予約」からご予約をお願いします。
あわせて読みたい
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会