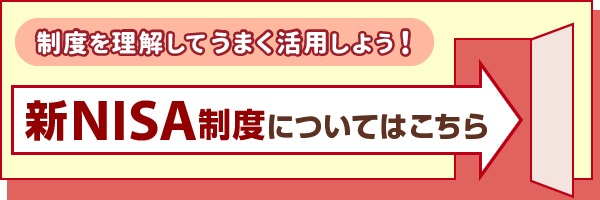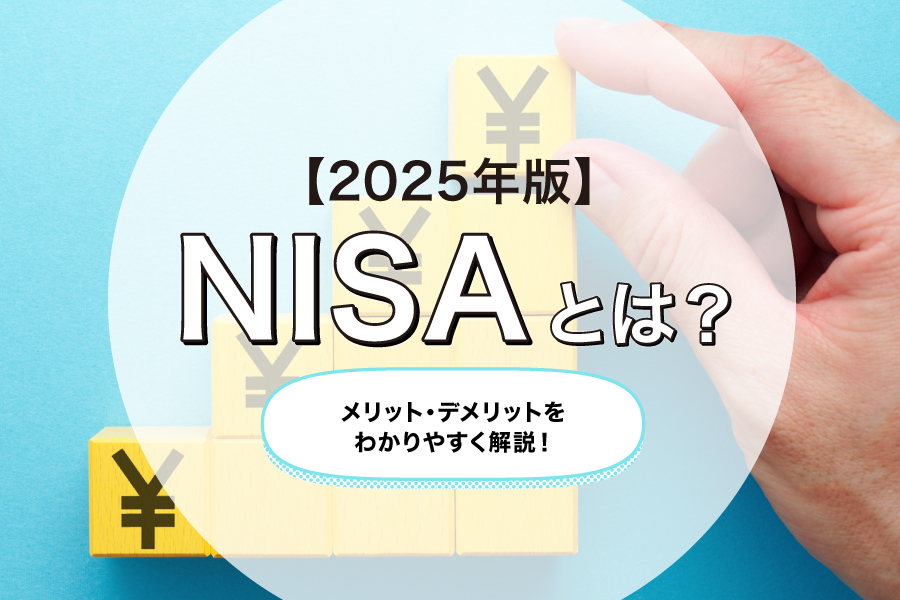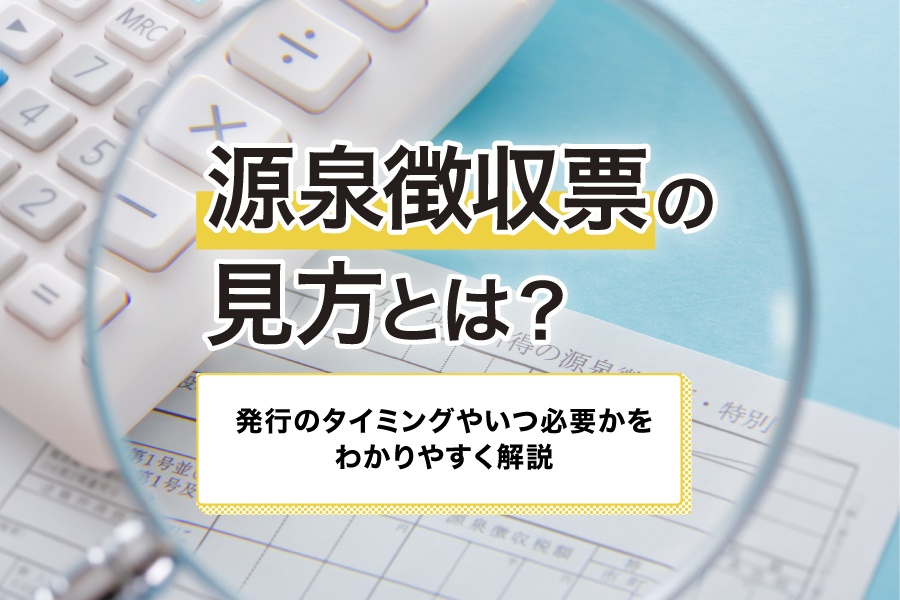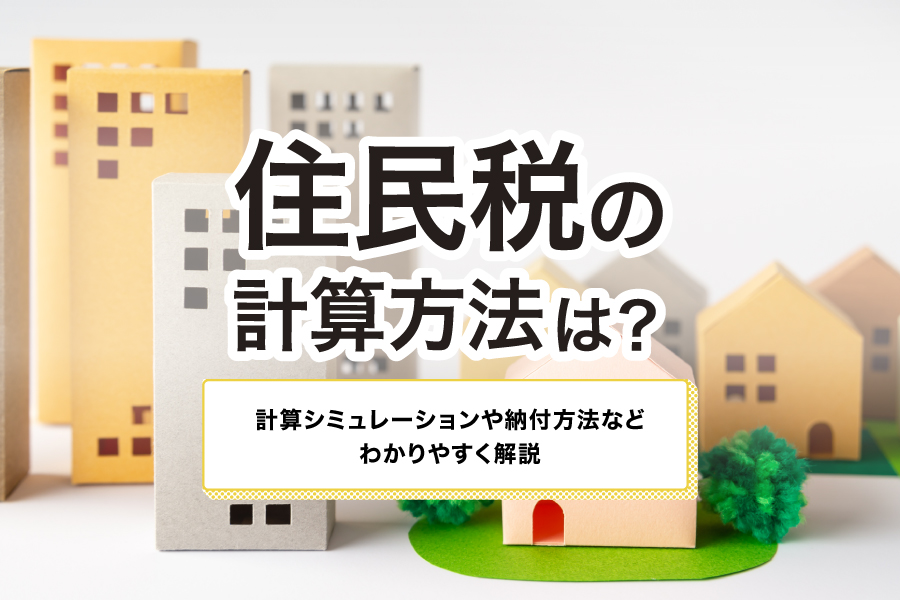投資信託の選び方7つのポイント。不安ならまずは「つみたてNISA」から

- 2020年12月14日
- 2023年12月29日
投資初心者にも人気の「投資信託」ですが、種類が多すぎてどうやって選んだらいいのかわからず、迷ってしまうという人も多いのではないでしょうか。そこで、投資信託選びで押さえておきたいポイントを7つ紹介します。
目次
投資信託の選び方1.どんな資産に投資するのか知ろう
一口に投資信託と言っても、投資対象が「株式」か「債券」か「不動産」か「その他資産」か、投資エリアは「国内」か「海外」かなど、いくつもの種類に分類されています。
投資対象やエリアなどの組み合わせによりその投資信託の特徴が変わってきます。一般的には、債券よりも株式の方が価格変動が大きかったり、投資エリアが海外だと為替相場の影響を受けたりといった特徴があります。つまり、期待リターンが大きいほど、リスクも大きくなり、期待リターンが小さいほど、リスクも小さくなります。
自分はどんな投資先を選びたいのか、どのくらいのリスクを許容できるのか考えてみましょう。ファンドの運用方針、リスク、運用実績、手数料等の費用などの重要事項がまとめられた書類である「目論見書(もくろみしょ)」を見れば、その投資信託の詳細を確認することもできますよ。
投資信託の選び方2.手数料や信託報酬を必ずチェックしよう
その投資信託でいくらお金がふえるのか正確に予測することはプロでも難しいですが、いくらコストがかかるのかは事前に確認することができます。
同じ運用結果なら、購入時手数料(購入にかかる費用)や信託報酬(運用にかかる費用)を安く抑えるほど手元に残るお金が多くなります。投資信託を選ぶうえでコストの確認は必須です。
投資信託の選び方3.純資産総額がある程度大きい銘柄を選ぼう
純資産総額(資産残高)は「基準価額(投資信託1口または1万口あたりの値段)×総口数(購入された数)」のことで、投資信託の規模を表します。
運用がうまくいっていたり、人気があったりすると純資産総額が増えます。規模が大きな投資信託は、多くの投資家から支持を集めていると言えるでしょう。同じ特性を持つ投資信託であれば、純資産総額が多い方を選ぶ、といった選択肢もあります。
投資信託の選び方4.ランキングや流行はあくまで参考程度に
ちまたに溢れるランキング情報。ただし、商品ランキング1位=リターンを保証するというわけではありません。複数のランキングを参考にすればそのときのトレンドはつかめますが、それはあくまで選ぶときの参考程度にとどめましょう。
周りに流され過ぎず、自分が希望する投資方針と合っているかを冷静に確認したいところです。
投資信託の選び方5.「高分配」や「毎月分配」だから良いとは限らない
分配金が多い、毎月分配金を受け取れる、ということは、その分投資に回す金額を減らして今手元に受け取っていることになります。
長期間に渡って投資して複利の効果を活かすなら、今手元に少額を受け取るよりも、できるだけ多くの金額を投資に回した方が効率よくお金をふやすことができます。
- 将来に備えて大きくふやしていきたいのか
- 毎月少しずつお金が入る幸せを優先させたいのか など
自分が何を目指すのか明確にし、その条件に合っている商品を選びましょう。
投資信託の選び方6.将来の予測が難しい場合は過去の運用成績も参考にしよう
投資信託では、過去の運用成績がカンタンに確認できます。過去の運用成績が良いからといって今後もそれが続くとは限りませんが、一つの参考値にはなるでしょう。
ファンドの過去の運用成績を見る指標の1つにトータルリターンというものがあります。これは一定期間のファンドの総合的な運用成績を表すものです。
過去の結果は将来を予測するものではないのでそれだけにとらわれず、投資対象資産の将来性を見極めるようにしましょう。
投資信託の選び方7.シャープレシオを確認しよう
シャープレシオとは、リスクに対しどれくらいのリターンを得られるかの目安になります。基本的に数字が大きいほど、同じリスクでも高いリターンを得られる「効率のよい投資」だと判断します。
世の中には多くの投資信託がある中、今までに挙げた7つの選び方のそれぞれの指標等を自分で探して比べるのは難しいかもしれません。そんなときは、各金融機関のホームページで指標毎に、投資信託を絞り込める機能を活用するのがよいでしょう。
投資信託の商品選びに迷う人は、「つみたてNISA」から始めてみよう
投資信託の購入を考えるなら、「つみたてNISA」についても確実に知っておきたいところです。つみたてNISAは、国が用意した税制優遇制度です。
この制度では、毎年40万円の投資枠が最長20年間にわたって利用できます。投資で得た利益には通常約20%の税金がかかりますが、この投資枠の範囲内だといくら利益を上げても非課税です。
「投資信託選びに迷ったらつみたてNISA」はなぜ?
つみたてNISAは、通常のNISAと違い投資できる商品がかなり限定されています。
- 購入時手数料ゼロ(ノーロード)
- 信託報酬は一定水準以下(例:国内株のインデックス投信の場合0.5%以下)
- 分配頻度が毎月ではない
このような条件をクリアした「金融庁が長期・分散・積立投資に適していると判断した投資信託」にしか投資できないようになっていますので、投資初心者でもこの中から選べば比較的失敗しにくい投資を実践できるでしょう。
投資信託選びのポイントを押さえて、納得できる投資先を探そう
投資信託選びに迷ったら、ここで紹介したようなポイントを思い出して、ホームページの機能等も活用しながら少しずつ商品を絞り込んでいくとよいでしょう。まずは自分の考えに合ったお気に入りの銘柄を選んで始めてみましょう。
執筆者:株式会社ZUU
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
あわせて読みたい
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
「NISA」制度をご利用の際は、次の点にご注意ください。
- 当行でNISA口座を開設するには、投資信託口座が必要です。
- NISA制度では、すべての金融機関を通じて1人につき1口座しか開設することはできません(金融機関の変更を行った場合を除く)。
- NISA口座は、店頭でお申し込みの場合、原則として、お申込日当日(お申し込みが休日の場合または当行所定の時刻までに受付手続が完了しなかった場合は翌営業日)、三菱UFJダイレクト(インターネットバンキング)の場合、最短でお申込日当日に開設します(*)。NISA口座では、開設と同じ日またはそれ以降に投資信託を購入することが可能です。口座開設後に行う税務署審査の結果、二重口座であったことが判明した場合、NISA口座で購入した投資信託は当初から課税口座で購入したものとして取り扱います。当該投資信託から生じる配当所得および譲渡所得等については、遡及して課税されます。
- 当行または他金融機関で、2018年以降のNISA口座の開設をお申し込み(2017年以前のNISAが継続した場合を含みます)されたことがある場合、当該口座は、税務署の審査が承認となり、当行所定の手続きが完了した後に開設されます(通常、お申し込みから2~3週間程度で手続きは完了します)。
- NISA口座は、開設後、税務署の審査が完了するまで金融機関の変更および廃止はできません。
- NISA口座での損失は税制上ないものとされます。
- NISA制度では、年間の非課税投資枠(つみたて投資枠は年間120万円、成長投資枠は年間240万円)と非課税保有限度額(総枠)(つみたて投資枠・成長投資枠あわせて1,800万円、うち成長投資枠1,200万円)の範囲内で購入した上場株式等の商品から生じる配当所得および譲渡所得等が非課税となります。
- 上場株式等の配当等はNISA口座を開設する金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
- 基準経過日において、NISA口座を開設しているお客さまの氏名・住所を、所定の方法で確認します。
- NISA取引は「受渡日」が属する年の非課税投資枠を利用します。なお、購入における「受渡日」は「約定日の翌営業日」です。「購入日」が「月末日」等で、「投信つみたて」の12月購入分の「受渡日」が翌年となる場合は、翌年の非課税投資枠を利用します。
- 当行のNISA(つみたて投資枠・成長投資枠)では、株式投資信託のみを取り扱いしております。
- つみたて投資枠での購入は、つみたて契約(投資信託継続購入プラン)に基づく、定期かつ継続的な方法により行うことができます。
- つみたて投資枠の対象商品は、長期のつみたて・分散投資に適した一定の投資信託に限られます。
- つみたて投資枠・成長投資枠に係るつみたて契約(投資信託継続購入プラン)による購入、成長投資枠で購入した投資信託の信託報酬等の概算値を、原則として年1回通知します。
- 成長投資枠の対象商品は、NISA制度の目的(安定的な資産形成)に適した一定の投資信託に限られます。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
株式会社 三菱UFJ銀行
(2024年12月20日現在)