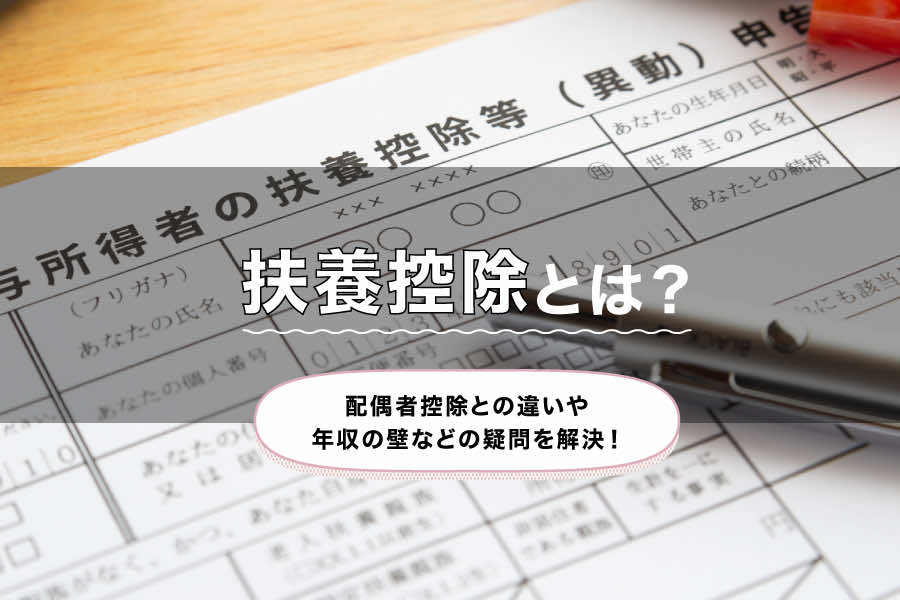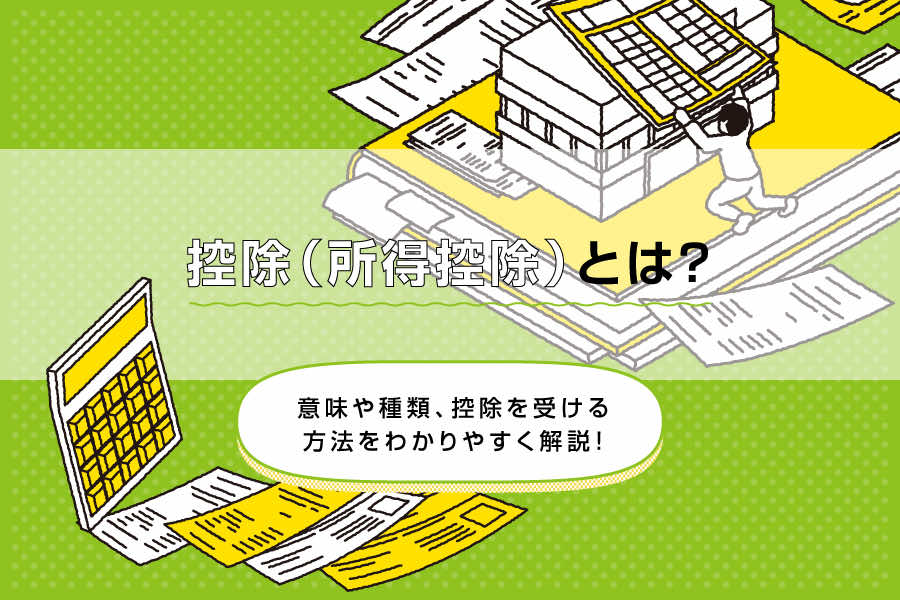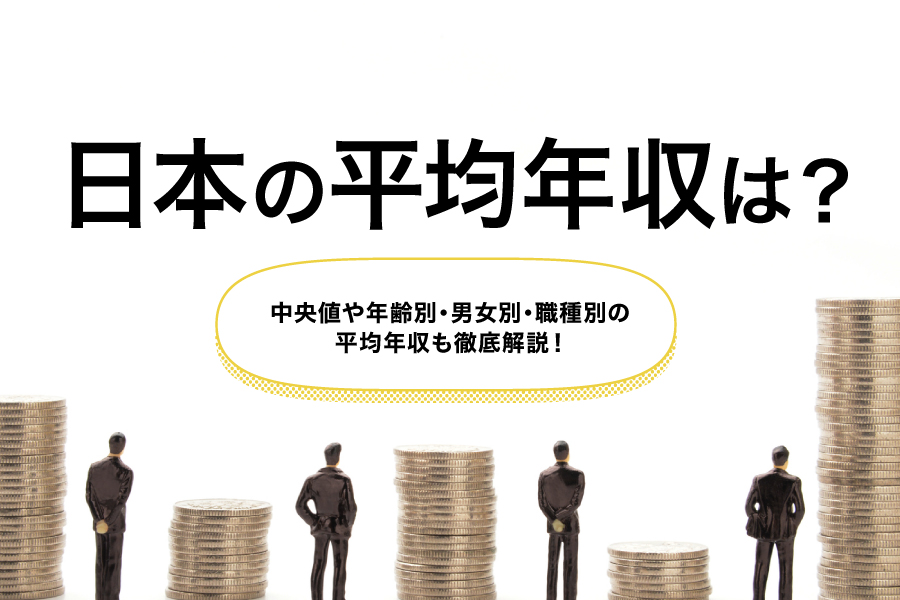配偶者控除・配偶者特別控除とは?違いや年収の壁をわかりやすく解説!

- 2025年10月30日
-
 この記事はこんな方におススメ!
この記事はこんな方におススメ!
-
 配偶者(特別)控除とは何か知りたい方
配偶者(特別)控除とは何か知りたい方
-
 年収の壁の最新情報について知りたい方
年収の壁の最新情報について知りたい方
配偶者の収入が一定の基準を下回ると配偶者控除と配偶者特別控除を受けられ、納税者本人の所得税・住民税の負担を軽減できます。2025年(令和7年)の税制改正により、配偶者控除と配偶者特別控除を受けるための配偶者の収入の基準が変わる点に注意が必要です。
この記事では税制改正をふまえ、配偶者控除と配偶者特別控除についてわかりやすく解説します。
目次
配偶者控除とは?
2025年の税制改正による基礎控除と給与所得控除の引き上げで、配偶者控除の対象となる配偶者の年収上限が上がりました。配偶者控除が適用される年収の範囲が広がり、働く時間をふやせるようになったのです。最初に、配偶者控除とはどのようなものかを見ていきましょう。
配偶者控除とは何か
配偶者控除とは所得控除の一種で、納税者に条件を満たす控除対象配偶者がいる場合に受けられます。控除を受けるのは、配偶者を扶養している納税者本人です。
2025年の税制改正により、適用の条件となる控除対象配偶者の年収(給与のみの場合の収入額)は103万円以下から123万円以下になります。配偶者に給与以外の所得があるときは、合計所得金額は58万円以下が条件となります。控除額は、納税者本人の合計所得金額によって異なる仕組みです。
また、控除対象配偶者の年齢が、その年の12月31日時点で70歳以上の場合は「老人控除対象配偶者」となり、通常の配偶者控除よりも高い控除額が適用されます。
配偶者控除を受けるための条件
納税者が配偶者控除を受けるには、控除対象配偶者がその年の12月31日時点で、以下のすべての条件に該当している必要があります。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 年間の合計所得が58万円以下であること(給与のみの場合は、給与収入が123万円以下)
- 青色申告者の事業専従者でその年に給与を一度も受け取っていないか、白色申告者の事業専従者でないこと
-
国税庁「No.1191 配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
また、上記の控除対象配偶者の条件以外に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるという条件を満たす必要があります。

配偶者特別控除とは?
配偶者特別控除は、控除対象配偶者の所得が配偶者控除の対象範囲を超えた場合でも、段階的に控除を受けられる制度です。配偶者控除から外れた世帯の税負担を急激に増加させないように設けられました。ここでは、配偶者特別控除について見ていきましょう。
配偶者特別控除とは何か
配偶者特別控除は、控除対象配偶者の年収(給与のみの場合の収入額)が123万円を超え、201.6万円未満の場合に適用される所得控除です。配偶者控除の対象から外れる年収であっても、201. 6万円未満であれば段階的に控除を受けられます。配偶者に給与以外の所得があるときは、合計所得金額が58万円超133万円以下であることが条件となります。
配偶者特別控除を受けるための条件
納税者が配偶者特別控除を受けるには、控除対象配偶者がその年の12月31日時点で、以下のすべての条件に該当している必要があります。
- 民法上の配偶者であること(内縁関係は該当しない)
- 納税者と生計を一にしていること
- 合計所得金額が58万円超133万円以下である(給与収入のみの場合、123万円超201.6万円未満)
- 青色申告者の事業専従者でその年に給与を一度も受け取っていないか、白色申告者の事業専従者でないこと
- 配偶者が配偶者特別控除を適用していないこと
- 配偶者が源泉控除対象配偶者として源泉徴収されていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合を除く)
- 配偶者が公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として源泉徴収されていないこと(年末調整や確定申告で配偶者特別控除の適用を受けなかった場合を除く)
-
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
また、配偶者控除と同様に、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であるという条件を満たす必要があります。

配偶者控除と配偶者特別控除の共通点と違い
配偶者控除と配偶者特別控除はいずれも、一定の条件に該当すると、納税者本人が受けられる所得控除です。ここでは両者の共通点と違いについて解説します。
配偶者控除と配偶者特別控除の共通点
配偶者控除と配偶者特別控除の共通点として、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下という所得の制限が挙げられます。この所得金額を超える場合は、配偶者控除・配偶者特別控除のどちらも利用できません。
また、両者とも納税者本人の所得金額に応じて、控除額が段階的に減少する仕組みです。
配偶者控除と配偶者特別控除の違い
配偶者控除と配偶者特別控除の大きな違いは、控除対象配偶者の所得の範囲です。
配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が58万円以下、配偶者特別控除は、58万円超133万円以下です。
配偶者控除は、配偶者の年間合計所得金額が58万円以下、配偶者特別控除は、58万円超133万円以下です。
配偶者控除は、控除対象配偶者の所得が要件を満たす場合、納税者本人の合計所得金額によって控除額が決まります。一方、配偶者特別控除は、納税者本人に加えて配偶者の合計所得金額にも応じて控除額が変動する仕組みです。配偶者の合計所得が高くなるにつれて、控除額が段階的に少なくなっています。
配偶者控除と配偶者特別控除の控除額はいくら?
納税者本人が合計所得金額1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が133万円以下の場合は、配偶者控除か配偶者特別控除を受けられます。ここでは、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額によって、実際の控除額がいくらになるかを見ていきましょう。
配偶者控除・配偶者特別控除の控除額早見表
以下は、納税者本人と配偶者の年間の合計所得金額に応じた控除額を一覧表にまとめたものです。
横スクロールして確認
| 配偶者の合計所得金額 | 配偶者の収入が給与所得のみの場合の配偶者の給与等の収入金額 | 納税者本人の合計所得金額 (給与所得のみの場合の給与等の収入金額) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 900万円以下 (1,095万円以下) |
900万円超950万円以下 (1,095万円超1,145万円以下) |
950万円超1,000万円以下 (1,145万円超1,195万円以下) |
|||
| 配偶者控除 | 58万円以下 | 123万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 老人控除対象配偶者 | 48万円 | 32万円 | 16万円 | ||
| 配偶者特別控除 | 58万円超 95万円以下 |
123万円超 160万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 100万円以下 |
160万円超 165万円以下 |
36万円 | 24万円 | 12万円 | |
| 100万円超 105万円以下 |
165万円超 170万円以下 |
31万円 | 21万円 | 11万円 | |
| 105万円超 110万円以下 |
170万円超 175万円以下 |
26万円 | 18万円 | 9万円 | |
| 110万円超 115万円以下 |
175万円超 180万円以下 |
21万円 | 14万円 | 7万円 | |
| 115万円超 120万円以下 |
180万円超 185万円以下 |
16万円 | 11万円 | 6万円 | |
| 120万円超 125万円以下 |
185万円超 190万円以下 |
11万円 | 8万円 | 4万円 | |
| 125万円超 130万円以下 |
190万3,999円超 197万1,999円以下 |
6万円 | 4万円 | 2万円 | |
| 130万円超 133万円以下 |
197万1,999円超 201万5,999円以下 |
3万円 | 2万円 | 1万円 | |
| 133万円超 | 201万5,999円超 | 0円 | 0円 | 0円 | |
-
国税庁「No.1195 配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
「年収の壁」はいつからどう変わる?

2025年の税制改正により、配偶者の扶養の範囲で働く方の「年収の壁」が変わります。年収の壁のボーダーラインとなる控除対象配偶者の所得基準が引き上げられたため、これまでより多く働いても、納税者が控除を受けられる範囲が広がりました。
この改正は2025年分の所得から対象になるため、2025年12月の年末調整や2026年の確定申告で適用されます。
ここでは、4つの年収の壁がどのように変わるのかを、ケーススタディとともに解説します。
なお、ケーススタディでは、配偶者控除と配偶者特別控除以外の年収の壁は考慮していません。
なお、ケーススタディでは、配偶者控除と配偶者特別控除以外の年収の壁は考慮していません。
【103万円の壁→123万円の壁】配偶者控除適用の範囲
2025年の税制改正で、基礎控除額と給与所得控除額がそれぞれ10万円ずつ引き上げられました。それにともない、配偶者控除を受けるための配偶者の年収上限が、103万円から123万円に引き上げられました。配偶者の年収が123万円までであれば、納税者はこれまでどおり最大38万円の配偶者控除を受けられます。
【ケーススタディ1】パート年収103万円のAさんと夫Bさんの場合
これまでAさんはパート年収を103万円以下になるように抑えて働いていました。2025年分からは、年収が123万円までなら課税されず、夫Bさんも配偶者控除を受けることができます。その結果、Aさんの収入増加分は、そのまま家計の収入増加分となります。
【150万円の壁→160万円の壁】配偶者特別控除を満額受け取れる範囲
2025年の税制改正で、配偶者特別控除を満額受けるための配偶者の年収上限が、150万円から160万円に引き上げられました。配偶者の年収が160万円までであれば、納税者は最大38万円の配偶者特別控除(配偶者控除と同額)を受けられます。
【ケーススタディ2】年収155万円のCさんと夫Dさんの場合
これまで、年収155万円のCさんの夫Dさん(年収800万円)の配偶者特別控除の控除額は36万円でした。2025年分からはCさんの年収が160万円までであれば、Dさんは満額の38万円の配偶者特別控除を受けられるようになります。その結果、Dさんの税負担が軽減され、家計の手取り収入が増加します。
【201万円の壁→変更なし】配偶者特別控除の配偶者の年収上限
「201万円の壁」とは、配偶者特別控除が適用されなくなる年収の上限で、2025年の税制改正においても変更されません。配偶者の年収201.6万円以上になると、納税者本人は配偶者控除も配偶者特別控除も受けられません。
【ケーススタディ3】年収200万円から210万円にふえたEさんと夫Fさんの場合
2024年のEさんのパートの年収は200万円だったため、夫Fさんは配偶者特別控除を受けていました。ところが、2025年にEさんの時給が上がり、年収が210万円になると、Fさんは配偶者特別控除を受けられなくなります。結果として、Eさんの収入が上がっても、Fさんの税負担がふえるため、手取りはあまりふえないことになります。
【1,000万円の壁→変更なし】納税者本人の年収上限
「1,000万円の壁」とは、納税者本人が配偶者控除と配偶者特別控除を適用される合計所得金額の上限で、2025年の税制改正においても変更されません。給与収入のみの場合は、年収1,195万円を超えると控除を受けられなくなります。
【ケーススタディ4】年収が1,000万円を超えるGさんと妻Hさんの場合
Gさんの2024年の合計所得金額は800万円だったため配偶者控除の適用となっていましたが、2025年には1,000万円を超える見込みです。そのため、妻Hさんの合計所得金額が2024年と変わらず100万円であっても、Gさんは2025年には配偶者控除を受けられなくなります。

配偶者控除・配偶者特別控除以外の「年収の壁」
配偶者控除と配偶者特別控除以外にも、所得税や住民税、社会保険に関する年収の壁が存在します。配偶者控除や配偶者特別控除の条件を満たしても、収入増によってほかの年収の壁を超えてしまう可能性もあるのです。ここでは、注意が必要な税金と社会保険の年収の壁について解説します。
税金の「年収の壁」
配偶者控除・配偶者特別控除とは別に、納税者本人の収入に対して税金がかかり始める「年収の壁」があります。
所得税は、2025年の税制改正により、年収123万円を超えると課税されます。基礎控除58万円と給与所得控除65万円の合計123万円を超えた部分に対して所得税が発生するためです。
住民税は、2025年の税制改正により、年収110万円を超えると課税されます。これは住民税の給与所得控除額の引き上げにともなう変更です。住民税は前年の年収に対して課税されるため、2026年度に支払う住民税から反映されます。
つまり、年収110万円を超えると住民税が発生し、年収123万円を超えると住民税と所得税の両方が課税されます。
社会保険の「年収の壁」
社会保険には、「106万円の壁」と「130万円の壁」があります。
106万円の壁は、従業員数51人以上の企業で働く短時間労働者が対象となります。週20時間以上勤務し、月額8.8万円以上(年収約106万円)となると厚生年金や健康保険への加入義務が発生します。この収入の基準は、2025年6月から3年以内に撤廃される予定です。
一方、130万円の壁は、配偶者の社会保険の扶養から外れる基準です。年収が130万円を超えると配偶者の扶養から外れ、勤務先の社会保険に加入するか、自分で国民健康保険や国民年金に加入する必要があります。
以下は、年収の壁をまとめた表です。配偶者控除と配偶者特別控除については控除対象の配偶者の年収、その他については納税者本人の年収が基準となります。
| 年収 | 住民税 | 所得税 | 社会保険 | 配偶者控除・ 配偶者特別控除 |
|---|---|---|---|---|
| 106万円以下 | かからない | かからない | 扶養加入可 | 配偶者控除 |
| 106万円超 | かからない | かからない | 対象者のみ加入 | 配偶者控除 |
| 110万円超 | かかる | かからない | 対象者のみ加入 | 配偶者控除 |
| 123万円超 | かかる | かかる | 対象者のみ加入 | 配偶者特別控除 |
| 130万円超 | かかる | かかる | 加入 | 配偶者特別控除 |
| 160万円超 | かかる | かかる | 加入 | 配偶者特別控除 |
| 201.6万円超 | かかる | かかる | 加入 | 適用されない |
-
首相官邸「年収の壁対策」
https://www.kantei.go.jp/jp/headline/nennsyuunokabe/index.html

配偶者控除・配偶者特別控除の手続き
配偶者控除・配偶者特別控除を受ける手続きは、給与所得者であれば基本的に年末調整で、個人事業主は確定申告で行います。
給与所得者の場合、年末調整時に勤務先から配付される「給与所得者の配偶者控除等申告書」に必要事項を記入して提出します。
個人事業主の場合は、確定申告書での手続きが必要です。確定申告書第一表の所得控除「配偶者(特別)控除」欄に控除額を記入し、第二表の「配偶者や親族に関する事項」欄に配偶者の氏名、生年月日、個人番号などを記入します。
まとめ
2025年の税制改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の年収は123万円以下、配偶者特別控除の満額適用を受ける配偶者の年収は160万円以下となります。これまでより配偶者が多く収入を得ても、納税者本人が配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる可能性があり、家計にうれしい改正といえます。
具体的にふやせる就業時間を確認し、無理のない範囲で収入増をめざしてはいかがでしょうか。
執筆者:松田 聡子(まつだ さとこ)
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、DCアドバイザー、二種外務員資格
執筆者保有資格:日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®認定者、DCアドバイザー、二種外務員資格
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
あわせて読みたい
株式会社 三菱UFJ銀行
(2025年10月30日現在)
(2025年10月30日現在)