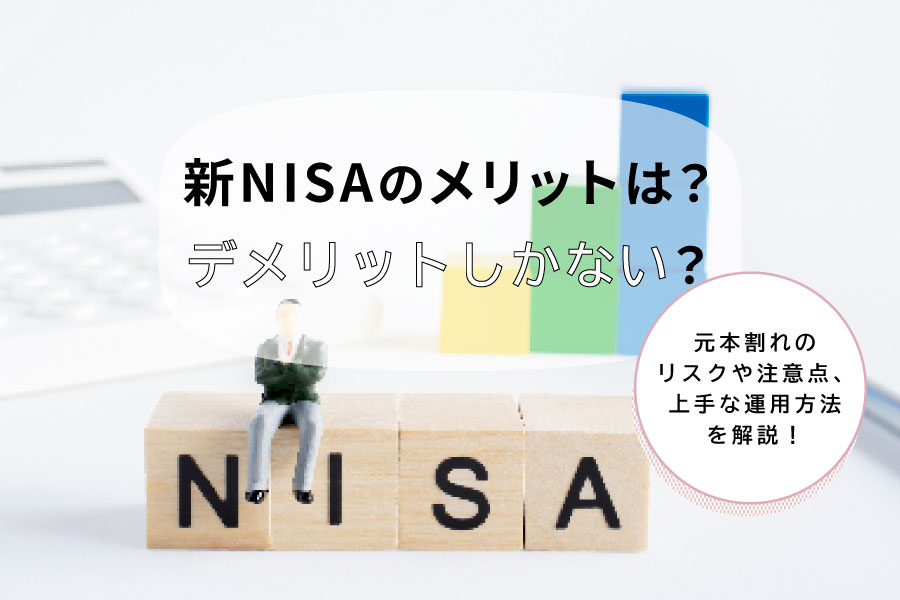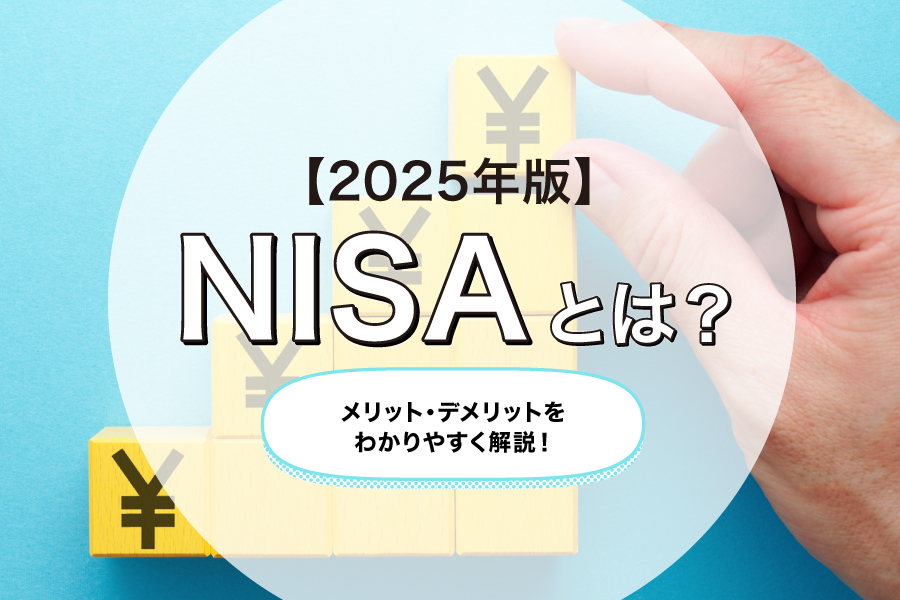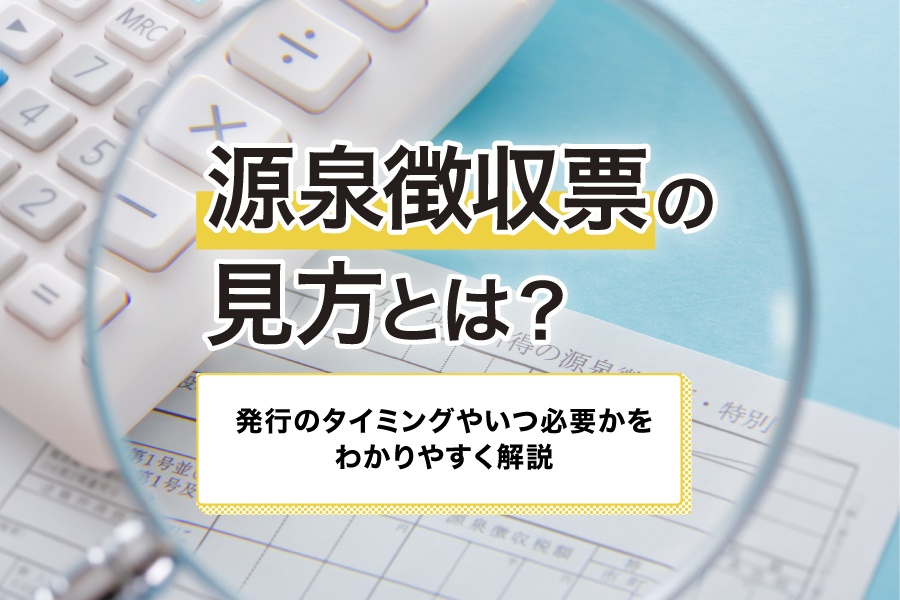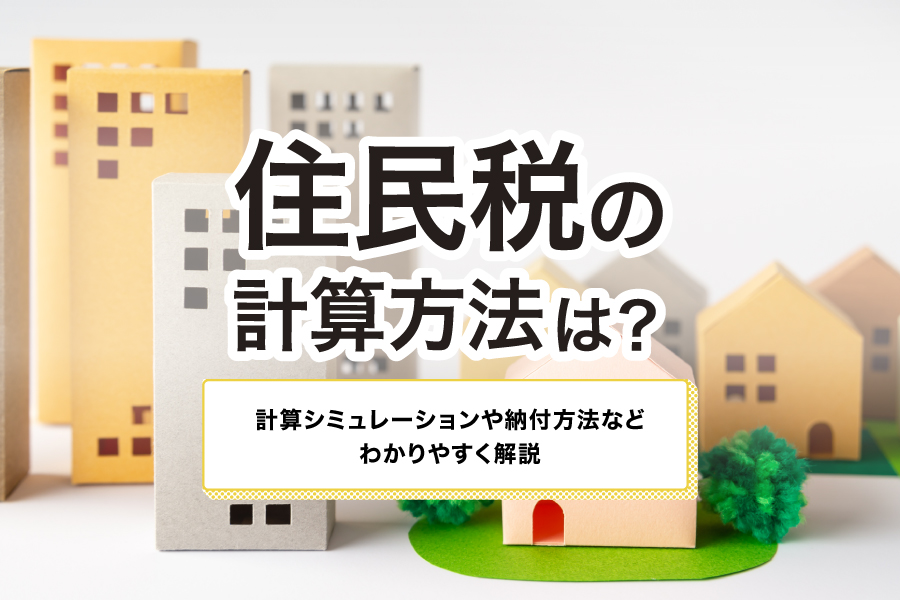投信積立とは?初心者にぴったりのはじめ方と商品選びをくわしく解説

更新日:2025年10月29日
投資に興味はあっても、どのような商品を選べばいいのかわからず、なかなかはじめることができない人も多いでしょう。
そのような人にとって、比較的はじめやすいとされている投資方法のひとつが「投信積立(投資信託の積立)」です。
そのような人にとって、比較的はじめやすいとされている投資方法のひとつが「投信積立(投資信託の積立)」です。
この記事では、投信積立とはどのような仕組みかを解説するとともに、そのメリットや注意点、そして初心者にもやさしい税制優遇制度を活用した始め方についてご紹介します。
目次
投資信託の買い方は2種類

投資信託(投信)をはじめとした金融商品の買い方は「一括購入」と「積立購入」の大きく2つに分けられます。
一括購入と積立購入はどちらがいい?
一度にまとまった金額で購入する一括購入と、一定の金額で継続的に購入を続ける積立購入は、どちらもメリットとデメリットがあるので、どちらか一方がよいということはありません。ただし、それぞれの特徴を踏まえると、投資初心者には積立購入のほうがはじめやすいと考えられます。
そこで、この記事では投資の中でも比較的はじめやすい投資信託を積立購入する、「投信積立」についてくわしく解説していきます。
投信積立とは
投資信託についておさらいしましょう。
投資信託(投信)は、個人の投資家から集めた資金を1つにまとめ、投資のプロが運用する金融商品です。それぞれの商品は、国内外の「株式」や「債券」などさまざまな金融商品に分散して投資し、運用の成果を個人投資家に分配する仕組みになっています。
この「投資信託」を毎月1,000円、5,000円、1万円など、一定の金額で積み立てる投資方法を「投信積立」と言います。
\少額からコツコツはじめる投信つみたて/
\少額からコツコツはじめる投信つみたて/
投信積立のメリット

投信積立のメリットには、「積立購入」のメリットと「投資信託」のメリットが揃っています。どんな点があげられるかチェックしてみましょう。
毎月自動で積み立て!手間いらず
投信積立は、最初に投資する商品(ファンド)を決めて、毎月の積立金額を設定すれば自動的に購入されるため、そのあとの購入に関する手続きは必要ありません。
一括購入の場合は、"安いときに買って、高いときに売る"ことで利益を出すことになるため、市場の動向や価格の変動が気になるでしょう。これに対して、投信積立は自分で売買のタイミングを計る必要がないので、「いつ買ったらいいのか、いつ売ったらいいのか」と悩むことなく、投資することができます。
少額からはじめられるので投資初心者にぴったり!
投資には、何十万円ものお金が必要と考えている人も多いでしょう。実際に株式を購入するのには一般的に大きなお金が必要ですし、投資信託を一括購入する場合も、ある程度まとまったお金で投資をすることが多いでしょう。
一方で、投信積立は少額からはじめられるのが大きな魅力です。金融機関によって最低投資金額は異なりますが、銀行などの場合は1,000円程度から、ネット証券などでは100円からはじめられるケースもあります。
購入するタイミングを分散してリスクを抑える!
投資信託の値段(基準価額)は、株価のように値動きがあり、安くなったり高くなったりします。購入する口数(購入単位のこと)を決めて買う場合は、この値段が安いときも高いときも当然ながら買う量は同じです。
これに対し、毎月5,000円、1万円など一定の金額を決めて買う場合は、安いときに多く買って、高いときに少なく買うことができ、長く続けるほど購入価格を平準化できます。これはドル・コスト平均法といってリスク分散の方法として広く知られており、積み立て方式で投資する大きな特徴です。
投資信託の注意点

ここまで紹介した以外にも、投信積立のメリットはたくさんありますが、いくつか注意点もあります。
投資信託は手数料がかかる!
まず気をつけたいのが、投資信託は運用のプロに任せるため、その分、さまざまな手数料がかかる点です。おもな手数料として次のようなものがあります。
- 販売手数料(投資信託を購入するとき)
- 信託報酬(投資信託を保有している期間)
- 信託財産留保額(投資信託を換金するとき)
これらの手数料は一律ではなく、商品によって異なります。一方で、販売手数料のかからない「ノーロード」といった商品や、信託報酬が低い商品もあるので、チェックしてみるといいでしょう。投資信託を購入するときには、目論見書などで事前にこれらの手数料を確認することが大切です。
運用結果により価格の変動があり、元本は保証されない
投資信託は運用をプロに任せるといっても、必ず利益が出るというものではなく元本の保証はされません。元本割れするリスクがあることを想定しておく必要があります。
利益に対して、税金がかかる
投信積立をはじめとした投資では、その利益に対して20.315%の税金がかかります。投資で利益をあげても、その分を税金で引かれてしまっては結果的に元本程度しか手元に残らない、もしくは元本割れすることも考えられます。
特に少額から運用する場合、最初は大きな利益を期待できないので注意が必要です。
そこで利用したいのが、次に紹介する「NISA(少額投資非課税制度)」です。
投信積立はNISAのつみたて投資枠ではじめよう!

NISA(少額投資非課税制度)は、株式や投資信託で得た利益に対する税金が非課税になる制度です。2024年の改正で制度が見直され、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の2つが設けられています。
特に「つみたて投資枠」は、長期的かつ安定的な資産形成を支援するための投資枠です。そのため、初心者が投信積立を始めるなら、NISAのつみたて投資枠の活用を検討しましょう。
特に「つみたて投資枠」は、長期的かつ安定的な資産形成を支援するための投資枠です。そのため、初心者が投信積立を始めるなら、NISAのつみたて投資枠の活用を検討しましょう。
ここからは、NISAのつみたて投資枠の特徴を紹介します。
運用益が非課税
前述の通り、投資信託は通常、利益に対して20.315%の税金がかかります。
しかしNISAを利用することで、利益を非課税で受け取ることができるため、大きなメリットがあります。非課税期間は、2024年の制度改正により無期限となりました。
しかしNISAを利用することで、利益を非課税で受け取ることができるため、大きなメリットがあります。非課税期間は、2024年の制度改正により無期限となりました。
積み立てできる金額は?
投信積立をはじめとした投資は、一般的に金融機関が定めた範囲で任意の金額を投資することが可能です。一方で、NISAのつみたて投資枠の年間投資上限額は120万円です。1ヵ月では10万円が上限額となります。
対象となる投資信託の種類
NISAのつみたて投資枠で購入できる商品は、金融庁が定めた基準を満たした投資信託やETFに限定されています。長期的な資産形成を支援する制度の趣旨に沿って、低コスト商品のみが対象となっていることが特徴です。
選択肢がせまくなるのでは?と考える人もいるかもしれませんが、厳選されているからこそ安心して選ぶことができるとも考えられるでしょう。
選択肢がせまくなるのでは?と考える人もいるかもしれませんが、厳選されているからこそ安心して選ぶことができるとも考えられるでしょう。
\NISAのつみたて投資枠について/
\NISAのつみたて投資枠について/
積立はいくらからはじめるのがいいか

積み立てる金額は、貯蓄や収入を踏まえて、余裕資金の中で無理なく始めることが大切です。まずは毎月5,000円や1万円など少額から始め、慣れてきたら金額をふやしてもよいでしょう。
積み立ての目的を明確にすることも重要です。子どもの教育資金や老後資金など、具体的な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
また、定期的に積み立て状況を見直し、収入や支出の変動に応じて金額を調整することも大切です。これにより、無理なく長期的な資産形成が可能になります。
また、定期的に積み立て状況を見直し、収入や支出の変動に応じて金額を調整することも大切です。これにより、無理なく長期的な資産形成が可能になります。
どんな商品を選ぶといいか
投資信託には多くの種類がありますが、NISAでは商品選びがより重要になります。商品を選ぶ際には、自分のリスク許容度を踏まえて選ぶことが大切です。
たとえば、「複合資産型(バランス型ファンド)」はリスクを分散しやすく、安定した運用を目指す人に向いています。一方、「株式100%型」はリスクが高いものの、高いリターンを期待する人に適しています。
自分の投資目的やリスク許容度を考慮し、適切な商品を選びましょう。
たとえば、「複合資産型(バランス型ファンド)」はリスクを分散しやすく、安定した運用を目指す人に向いています。一方、「株式100%型」はリスクが高いものの、高いリターンを期待する人に適しています。
自分の投資目的やリスク許容度を考慮し、適切な商品を選びましょう。
できるだけリスクを抑えて運用したい
投資信託は、複数の金融商品に投資することでリスクを分散できる仕組みです。その中でも「複合資産型(バランス型ファンド)」は、株式、債券、REIT(リート)などを組み合わせて投資するもので、資産を分散させられることからリスクを抑えられることが特徴です。
この資産配分については、目論見書などに記されているので確認するようにしましょう。一般的に、株式の割合が小さいほど、リスクを抑えることができます。ただし、リスクを抑えるほどリターンも期待できなくなるという関係(ローリスク・ローリターン)です。
積極的にリターンを狙っていきたい
複合資産型に対して、もう一方の「株式100%型」は大きなリターンを狙うことが可能です。株式の値動きは債券に比べて大きい傾向があり、ほかの商品(債券など)と組み合わせないことで、リスクが高まるのと同時にリターンの期待も高まる(ハイリスク・ハイリターン)というわけです。
株式の中でも、「国内株式<外国株式(先進国)<外国株式(新興国)」の順でリスク(リターン)が大きくなると言われています。なお、株式100%型の場合は同じ投資先(たとえば「国内」など)であれば、商品名が異なっても中身はほとんど同じという傾向にあるので、手数料が低いものを選ぶとよいでしょう。
毎月コツコツ、投信積立をはじめてみよう!
投信積立は株式投資などと比べて、個人投資家の手間がかからず、リスクを抑えながら資産形成ができる投資の1つです。少額から購入できるので、投資初心者でも取り組みやすいでしょう。また、NISAのように運用益が非課税になる制度もできて、取り組みやすい環境が整ってきています。投資に興味がある人は、まずは投信積立からはじめてみませんか。
執筆者:黒木留美
ファイナンシャル・プランナー
AFP、ファイナンシャルプランニング技能士2級
※記事内の情報は更新時点のものです。最新情報は別途ホームページ等でご確認ください。
- 「Facebook」及びそのロゴマークは、Meta Platforms, Inc.の商標または登録商標です。
- 「X」及びそのロゴマークは、X Corp.の商標または登録商標です。
- 「LINE」及びそのロゴマークは、LINEヤフー株式会社の商標または登録商標です。
- 上記記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入・申込時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 上記記事の情報は、記事の公開日または更新日時点での情報であり、その正確性、完全性、最新性等内容を保証するものではありません。
- 一部、当行にて取り扱いのない商品に関する内容を含みますが、商標登録されている用語については、それぞれの企業等の登録商標として帰属します。
- 上記記事の内容は、予告なしに変更することがあります。
あわせて読みたい
投資信託をお申し込みの際は、次の点にご注意ください。
- 投資信託は預金ではなく、その基準価額は、組入れ有価証券(株式・債券等)の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回る場合があります。
- 組入れ有価証券等は、株式指標・金利等を原因とした値動きにより変動します。
- 投資信託の購入時手数料や運用管理費用(信託報酬・管理報酬等)・信託財産留保額等の手数料等はファンド・購入金額等により異なるため、具体的な金額・計算方法を記載することができません。
- お申込前に必ず最新の契約締結前交付書面(目論見書および目論見書補完書面)等を十分にご確認ください。
当行では「三菱UFJ銀行の投資信託口座」や「金融商品仲介口座」で投資信託をお取り扱いしております。
それぞれの口座について、くわしくはこちらをお読みください。
株式会社 三菱UFJ銀行
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
委託金融商品取引業者 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
株式会社 三菱UFJ銀行
(2025年10月29日現在)