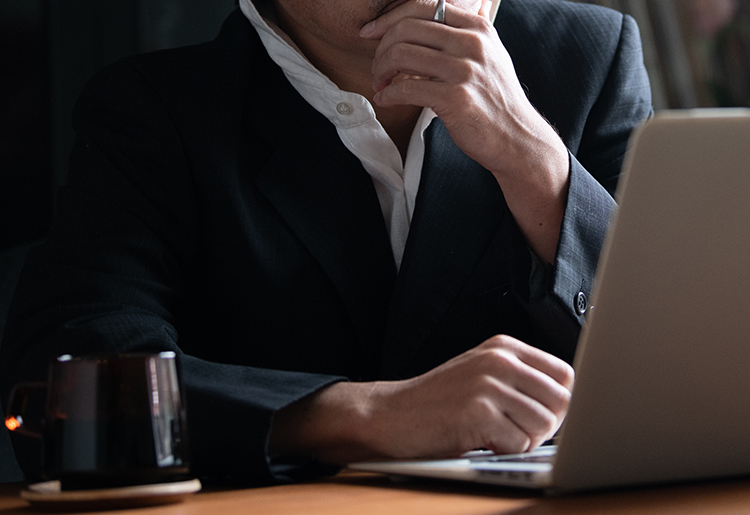農業における事業承継 大手企業参入やマッチングにより多様化する承継の形
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
日本農業の後継者問題
また、農林水産省の2020年農林業センサスでは、全国の農業経営体総数107万5,705のうち、5年以内に引き継ぐ後継者を確保しているのは26万2,278経営体と約4分の1にとどまっており、加えてそのうちの25万158経営体が親族内の後継者とされています。
農業経営体は、一般の中小企業以上に深刻な後継者不在問題に悩まされているといえるでしょう。
農業経営体の5年以内の後継者の確保状況
5年以内に引き継ぐ後継者の分類 |
経営体数 | 割合 |
|---|---|---|
| 親族 | 250,158 |
23.20% |
| 親族以外の経営内部の人材 | 8,712 | 0.80% |
| 経営外部の人材 | 3,408 | 0.30% |
| 5年以内の引き継ぎ予定なし |
49,060 | 4.60% |
| 確保できていない |
764,367 |
71.10% |
| 合計 | 1,075,705 | 100.00% |
農業経営体の動向
一方で農業経営体のうち、株式会社や農事組合法人などの法人経営体数は、2020年時点で3万707経営体となっており、2005年の1万9,136経営体から約1.5倍と増加傾向にあります。
農業経営体数とそのうちの法人経営体数
|
2005年 | 2010年 | 2015年 | 2020年 |
|---|---|---|---|---|
| 農業経営体数 | 2,009,380 | 1,679,084 | 1,377,266 | 1,075,705 |
| うち法人経営体数 |
19,136 | 21,627 | 27,101 | 30,707 |
農業経営を法人化することで経営管理が徹底され、事業発展が期待できるとともに、安定的な雇用の確保や円滑な事業承継が進めやすくなります。
また大手企業による農業分野への参入も目立っています。大手居酒屋チェーンのA社や、全国展開するレストランチェーンのB社、小売業大手のC社などは、その資本力と展開力を活かして農業分野に参入しています。
法人の農業参入
それまでは、農地の所有者により農地を耕作することが一般的とされてきましたが、高齢化や後継者不足等を背景に、農地所有者に限定せず、農地の適正かつ効率的な利用を促す方向に改正されました。たとえば、リース方式であれば、株式会社でも農地を借りることができるようになります。
農地を所有して農業を行う場合には、さまざまな要件が求められます。その要件を満たした法人を農地所有適格法人といい、要件を満たしていないと農地を所有できません。
一方で大幅に緩和されたリース方式は、農地所有適格法人ほどの要件はありません。その影響もあり、リース方式による農業経営法人は2019年12月末時点で3,669法人と、2009年の農地法改正前の約5倍のペースで増加しています。
法人の農業参入の2つの方式
方式 |
所有方式(農地所有適格法人) | リース方式 |
|---|---|---|
| 形態 | 株式会社(株式譲渡制限あり)、合名会社、合資会社、合同会社、農事組合法人 | 問わない |
| 農業割合 |
農地取得後の農業売上割合が50%超 | 問わない |
| 構成員 | 農業関係者が過半数の議決権を占めること | 問わない |
| 役員 |
|
役員または重要な使用人の1人以上が農業の常時従事者であること |
| 農地利用 |
|
|
| その他 |
|
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
農業の事業承継
事業承継とは、会社の経営権や資産を後継者へと引き継ぐことをいいます。まず、事業承継の3つの形と3つの要素について解説します。なお、詳細は以下をご覧ください。
事業承継の3つの形
事業承継は、誰に引き継ぐかによって3つの類型に分けられます。
1.親族内事業承継
冒頭で紹介したとおり、5年以内に後継者が決まっている農業経営体のほとんどが親族を後継者候補としています。
親族内事業承継であれば、一緒に農作業に従事してノウハウを後継者に承継しながら、高額な農業用設備などをそのまま引き継ぐことができます。
もっとも、農家の廃業は増加傾向にあり、廃業した場合は、農地の管理を農業協同組合や知り合いの農家に託すケースが多く見られます。
2.社内事業承継
3.親族外(第三者)への事業承継
メリットは事業を存続できることや従業員の雇用を守れること、株式や農地などを売却して資金をえられることなどがあります。もっとも、必ずしも希望額で売却できるとは限らず、事業承継が思うように進まないこともあります。
また第三者に譲渡する際には、その後継者が農業関係者とは限りません。農業関係者以外の人が農地を所有することには厳しい制約があります。
前述のとおり農地の所有方式(農地所有適格法人)か、リース方式かによって要件は変わり、特に農地所有適格法人として承継する場合は、さまざまな要件をクリアする必要があります。
これまでは後継者がいないことを理由に廃業を選択していた農業経営者が一定数いました。しかし最近は、大手企業の農業への参入に加え、事業承継のマッチング会社も増えており、廃業を検討する際は第三者への事業承継を選択肢として考えても良いでしょう。
事業承継で引き継ぐ3つの要素
1.経営権
経営権の承継とは、代表取締役など代表者としての地位と役割を後継者へと引き継ぐことです。そのために後継者を探す、あるいは育成することも大事になります。
実際に引き継ぐ際は、株主総会を経て代表取締役を選任した上で、役員変更登記等の手続きをする必要があります。
農業を引き継ぐ側は、所有方式かリース方式かによって、農業従事者等の構成員要件や役員要件などそれぞれの要件を満たさなければなりません。
2.経営資源の承継
経営資源とは、会社の経営理念や信用力、ブランド、独自に築いてきたノウハウや長年培ってきた技術、育てた人材や取引先をはじめとした人脈などを引き継ぐことです。
経営権を引き継ぐと同時に、オリジナルのブランドや栽培技術、関係を深めてきた仕入れ先といった経営資源を引き継ぐことでスムーズな承継が可能になり、逆に十分な引き継ぎができていないと、事業承継を機に会社が低迷してしまう可能性もあります。
3.物的資産の承継
会社が所有する不動産や設備、運転資金等は、株式を承継することで後継者へと自動的に引き継げます。しかし、オーナー経営者が個人で事業用資産を所有し会社に貸しているケースでは、事業用資産も併せて移転しておく方が良いでしょう。また、個人事業の場合、すべての事業用資産を個別に引き継がなければなりません。
後継者である法人が農地を所有する場合には、農地所有適格法人に該当していなければなりません。リース方式であれば要件は緩和されますが、一定の制約があります。
農業経営や農業の事業承継に対しては、さまざまな補助金や融資、税制などのサポートもあります。事業承継はまだ先のこと、とは考えず、早めに準備を進めるのが望ましいでしょう。
MUFGには銀行・信託・証券に加えて、さまざまな専門知識とノウハウをもったグループ関連会社やグループ内外の幅広いネットワークがあり、農業の事業承継においてもさまざまなニーズにお応えしています。
農業の事業承継は、農地法など業界特有の制約などもあるため、専門家のサポートを受けて進めることをおススメします。後継者の問題でお悩みを抱えている農業従事者の方は、MUFGウェルスマネジメントにぜひご相談ください。
-
銀行・信託・証券の専門チームがサポート
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
執筆者:八木正宣(税理士 / 行政書士 / CFP /1級FP技能士)
- 本記事は、2025年4月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。
- 本記事は情報提供を目的としており、投資等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 本記事は、当行が信頼できると判断した外部執筆者に執筆を依頼したものです。本記事の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますので予めご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
- 銀行からの融資には所定の審査があります。審査の結果、ご希望に沿いかねる場合があります。遺言信託や遺産整理業務等の相続関連業務については、当行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店としてお取り扱いいたします。当行は信託代理店として媒介をいたしますが、当行には、契約締結に関する権限はなく、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。IPO、M&A等の相談をご希望の場合は、当行は、お客さまのお申し出にもとづいてグループ会社をご紹介いたします。
MUFGウェルスマネジメント
ソーシャルメディアアカウント
- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。
- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
宅地建物取引業 届出第6号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会