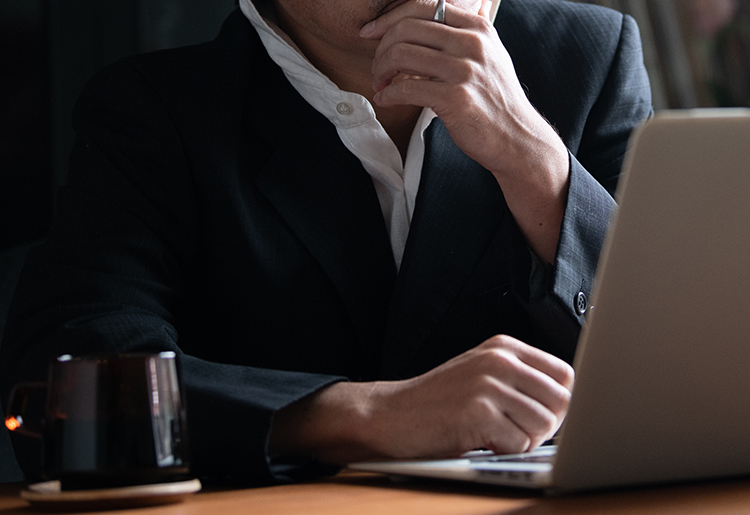個人事業主が事業承継するには? 手続きや税金について知る
個人で不動産業を営んでいたり、独立して成功を収めたり、個人事業主として資産を築いた人たちは、自身が育てあげた事業をどのようにして後継者に引き継いでいくのでしょうか。
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
法人と個人事業主の違い
法人、個人事業主それぞれの定義
法人は、登記によって法律上の人格が認められるようになり、経営者が代わっても経営者の持っている株式や出資を後継者に承継することにより、法人の経営権や財産権を包括的に引き継ぐことができます。
一方、個人事業主とは、個人が主体となって事業を営む者をいいます。経営権も財産権も、事業主1人に属していることが特徴です。
個人事業を後継者に承継するには、現事業主が所有する事業に必要な資産を後継者に引き継ぎ、後継者が新たに個人事業主となって事業を開始することで実現できます。
事業承継の前に個人事業を法人化し、法人として事業承継を行うことも可能ですが、ここでは、個人事業主として事業承継を行う方法について解説します。
なお、法人による事業承継については、こちらの記事でくわしく説明しています。
事業承継をする際に必要なこと
生前の事業承継において、税務署に対する提出書類
| 現経営者 |
※以下、必要に応じて提出
|
|---|---|
| 後継者 |
※以下、必要に応じて提出
|
社会保険や労働保険に関する手続き(年金事務所、ハローワーク、労働基準監督署)
営業の許認可申請や届出に関する手続き(各行政担当窓口)
屋号(商号)の登記に関する手続き(法務局等)
承継の方法によっては、現経営者や後継者に納税義務が発生し、税務申告と納税をしなければならなくなります。
個人事業主の事業承継
事業承継で引き継ぐもの
事業の経営権のこと。個人事業は株式等による承継はできません。現経営者の廃業と後継者の新規開業によって、経営権を承継します。
個人事業は、事業主が培った技術や信頼関係を軸に運営していることが多いため、計画的に後継者の育成に取り組む必要があります。
固定資産は、現経営者やその親族が個人で所有しているケースが多いため、それぞれを贈与や売却などの方法によって、後継者に引き渡す必要があります。その際、現経営者や後継者に税負担が生じることがあります。
事業承継の方法
事業用の資産を後継者に承継する方法には、贈与、相続、売却(M&A等)があります。それぞれ税や金銭の負担がかかり、いずれも後継者の負担が重くなる傾向にあります。
贈与を受けた後継者には、その評価額に対して贈与税の負担が生じますので、納税資金不足にならないよう注意しなければなりません。
なお、有償であれば贈与税が発生しないわけではなく、もし著しく低い対価で資産を売却すると、その資産の時価との差額が贈与とみなされ課税される場合があります。
相続や遺贈では、事業用の資産を含むすべての遺産に対し、相続税が発生します。贈与と同様、後継者の納税資金不足には注意が必要です。
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
税負担を抑える制度
相続時精算課税制度とは
子や孫に対する累計2,500万円までの贈与財産にかかる贈与税を非課税とし、贈与者の死亡時に、その贈与財産を相続税の課税対象として精算する制度です。
最終的に相続税は負担しなければなりませんが、生前に事業承継を進めたいニーズがある場合にはメリットがあります。
小規模宅地等の特例とは
被相続人(亡くなった人)の土地のうち、一定要件を満たす宅地の相続税評価額を減額できる相続税の特例です。
例えば、被相続人の事業用の宅地(相続開始前3年以内に事業用に供された宅地等[一定の場合を除く]は除外されます)を後継者が相続し、申告期限まで宅地を保有して、かつ、事業を継続するといった要件を満たせば、400㎡までの評価額を80%減額することができます。この要件を満たした事業用宅地(貸付事業用宅地等を除く)を特定事業用宅地等と呼びます。ただし、利用区分が異なる宅地等を複数所有している場合は、以下のいずれに該当するかに応じて限度面積を判定します。
- 特定居住用宅地等(被相続人または被相続人と同一生計の親族の居住用宅地等で一定の要件を満たしたもの)と特定事業用宅地等の両方がある場合(ただし、貸付事業用宅地等がない場合):特定居住用宅地等330㎡、特定事業用宅地等400㎡を限度として合計730㎡まで併用可能
- 貸付事業用宅地等がある場合の計算式は以下で算出
計算式:特定事業用宅地等×200/400㎡+特定居住用宅地等×200/330+貸付事業用宅地等≦200㎡を限度とする
個人版事業承継税制とは
経営承継円滑化法という法律の認定を受けた後継者が、一定の事業用資産を、現経営者やその親族から贈与や相続によって取得した場合、そこで発生する贈与税・相続税の納税が猶予される税制です。
さらに、猶予された状態で一定要件を満たすと、最終的に納税義務が免除されます。
この制度の大まかな流れは、まず納税猶予のための手続きをし、その後、免除の要件を満たした際に免除の手続きを行うものになります。
納税猶予の対象になる事業用資産・事業内容・後継者・贈与者や被相続人(経営者やその親族)には、それぞれ以下の要件があります。
- 事業用資産の要件
贈与や相続開始の前年分の事業所得にかかる青色申告書の貸借対照表に計上された資産のうち、以下のもの
建物(800㎡以下の部分)
次の減価償却資産
固定資産税の課税対象になるもの(機械、器具備品など)、一定の車両、生物(乳牛・果樹など)、無形固定資産(特許権など)
- 事業内容の要件
贈与や相続開始時において、資産管理事業や性風俗関連特殊営業に該当しないこと
- 後継者の要件
贈与の直前において(相続の場合は、相続開始の直前において)、その事業や同種の事業に従事している
期限内に、都道府県に個人事業承継計画を提出し、経営承継円滑化法の認定を受けている
期限内に、税務署に開業届出書・青色申告承認申請書を提出している
- 贈与者・被相続人の要件(経営者の場合)
贈与(相続開始)の年・その前年・前々年の確定申告を青色申告(青色申告特別控除55万円又は65万円が適用される申告)で行っている
税務署に廃業届出書を期限内に提出している(贈与のみ)
- 贈与者・被相続人の要件(経営者以外の場合)
法人版事業承継税制との違い
法人の事業承継にも同様の税制がありますが、違いは下記のとおりです。
個人版事業承継税制と法人版事業承継税制の違い
|
個人版事業承継税制 | 法人版事業承継税制 |
|---|---|---|
| 適用期限 | 2019年1月1日から2028年12月31日まで |
一般措置:期限なし |
| 経営承継期間・ 経営承継期間等 |
5年間 | 5年間 |
| 対象資産 | 特定事業用資産 | 非上場株式等 |
| 納税猶予割合 |
100% | 一般措置:贈与100%、相続80% 特例措置:100% |
| 継続届出書提出 |
3年ごとに提出 |
経営承継期間中は毎年提出、その後は3年ごとに提出 |
| 都道府県知事への 年次報告書提出 |
不要 | 経営承継期間中は毎年提出、その後は不要 |
| 青色申告要件 |
あり |
なし |
| 雇用確保要件 | なし | 一般措置:あり 特例措置:実質廃棄 |
法人版事業承継税制のくわしい内容は、こちらの記事をご覧ください。
個人版事業承継税制の手順
- 納税猶予を受けるための手続き
- 個人事業承認計画を作成し、都道府県に提出する
期限:2026年(令和8年)3月31日(贈与や相続の開始後であっても(2)の申請時までは提出可) - 贈与や相続開始の後、都道府県に円滑化法の認定申請をする
期限:(相続)相続開始後8か月以内、(贈与)翌年1月15日まで - 現経営者から税務署に廃業届出書を提出する(贈与のみ)
期限:廃業から1か月以内 - 後継者から税務署に開業届出書と青色申告承認申請書を提出する
期限:(開業届出書)開業から1か月以内、(青色申告承認申請書)※下記参照 - 後継者から税務署に相続税や贈与税の申告・担保提供を行う
申告期限:(相続税)相続開始の翌日から10か月以内、(贈与税)翌年3月15日まで
贈与の場合は事業開始から2か月以内、相続の場合は現経営者の死亡日によって下記のように変わります。
| 死亡日 | 提出期限 |
|---|---|
1/1~8/31 |
死亡の日から4か月 |
| 9/1~10/31 | 12月31日 |
| 11/1~12/31 | 翌年2月15日 |
- 納税猶予を継続するための手続き
- 毎年、所得税の青色申告を行う
- 3年ごとに継続届出書を税務署に提出する
- 納税猶予を受けた事業用資産の保有を続ける(※)
- 陳腐化による廃棄などは可能ですが、税務署への手続きが必要です
個人版事業承継税制の特徴
- 後継者が死亡した場合
- 贈与者が死亡した場合(贈与税の納税猶予のみ)
- 特定申告期限(*1)の翌日から5年を経過する日後に、免除対象贈与(後継者に対する、この制度を適用した事業用資産の贈与)を行った場合
- やむを得ない理由(一定の障害や介護状態になる等)で事業を継続できなくなった場合
- 破産手続開始の決定などがあった場合
- 事業の継続が困難な一定の事由(*2)が生じた場合において、事業用資産の譲渡・事業の廃止をした時
- 次のA、Bのいずれか早い日
A:この制度における後継者の最初の贈与税の申告期限
B:この制度における後継者の最初の相続税の申告期限 - A:直前3年内のうち2年以上で事業所得がゼロ未満である
B:直前3年内のうち2年以上で事業の総収入金額が前年比でマイナスである
C:後継者が心身の故障等で事業に従事できない
- 免除の手順
(1)から(4)は6か月を経過する日までに、税務署に免除届出書と必要書類を提出します。
(5)と(6)は2か月を経過する日までに、税務署に申請書と必要書類を提出します。
なお、「(2)贈与者が死亡した場合」について、贈与税の猶予中に贈与者(先代経営者など)が死亡した場合、贈与税は免除されますが、同時に、納税猶予中の事業用資産は相続によって取得したものとみなされ、相続財産の課税対象に加えられます。
この相続税も一定要件を満たせば猶予が継続され、さらに条件を満たせば免除されます。
個人版事業承継税制の留意点
- 事業を廃止した場合(やむを得ない理由による場合を除く)
- 資産管理事業等の特定の事業に該当した場合
- 事業所得の総収入金額がゼロになった場合
- 青色申告の承認が取り消された場合、取りやめの届け出をした場合
- 継続届出書を期限内に提出しなかった場合
個人版事業承継税制は、要件が複雑であるうえ、一つのミスで、それまでの納税猶予が水泡に帰すこともあります。専門家のサポートを受けながら実施すべきでしょう。
また多くの事業承継では、経営改善や後継者の育成も行わなければなりません。最初にきちんとした事業承継の方針と計画を立てることが、成功のカギとなります。
MUFGでは、事業承継計画の立案、贈与や相続のサポート、後継者の育成サポートなど多角的な支援が可能です。
-
銀行・信託・証券の専門チームがサポート
- お問い合わせ・ご相談はスパイラル株式会社が運営するサイトにて受け付けております。
執筆者:中村太郎(税理士 / 行政書士)
- 本記事は、2025年4月時点の税制、その他関連法規に基づく内容であり、今後の改正等により相違が生じることがあります。税法や法律に関わる個別、具体的なご対応は必ず税理士・公認会計士・弁護士等の専門家へご相談・ご確認ください。
- 本記事は情報提供を目的としており、投資等の勧誘目的で作成したものではありません。商品の購入時にはお客さまご自身でご判断ください。
- 本記事は、当行が信頼できると判断した外部執筆者に執筆を依頼したものです。本記事の情報は、当行が信頼できると判断した情報源から入手したものですが、その情報源の確実性を保証したものではありません。本記事の記載内容に関するご質問・ご照会等には一切お答えしかねますので予めご了承ください。また、本記事の記載内容は、予告なしに変更することがあります。
- 銀行からの融資には所定の審査があります。審査の結果、ご希望に沿いかねる場合があります。遺言信託や遺産整理業務等の相続関連業務については、当行は三菱UFJ信託銀行の信託代理店としてお取り扱いいたします。当行は信託代理店として媒介をいたしますが、当行には、契約締結に関する権限はなく、ご契約に際しては、お客さまと三菱UFJ信託銀行が契約当事者となります。
MUFGウェルスマネジメント
ソーシャルメディアアカウント
- FacebookロゴはMeta Platforms,Incの商標または登録商標です。
- YouTubeロゴはGoogle LLCの商標または登録商標です。
登録金融機関 関東財務局長(登金)第5号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
登録金融機関 関東財務局長(登金)第33号
加入協会 日本証券業協会 、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
宅地建物取引業 届出第6号
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2336号
加入協会 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会